+ 《変容の対象》2014年版
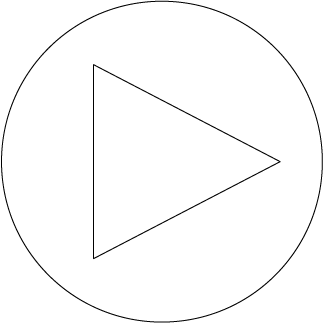 00:00 [00:00]
00:00 [00:00]
作曲: 濱地潤一 + 福島諭
《変容の対象》2014年版総括文
1月
冒頭文 neuroballet-hardcore(濱地)
神経バレイ・ハードコアという言葉からどういったイメージ、心象、あるいはシーンが浮かび上がるか、、、冒頭文が果たすこの作品の役割は決して軽いものではない。時に具体的なある種のコモンセンスを表す言葉を選ぶ時もあればこういった造語、ガイシンーバロウズの文脈を想起させる言語のカットアップ連結を自分は好んで記すようだ。動機はシンプルなもので、記憶をたどると実際にサックスで吹いたものを五線譜に記した。13小節目まではお互い探っているような組織が続く。冒頭文と組織が急速に近親性をもつのが14小節目からで、とにかく憑かれたような運動が起こっている。書いた当時の心象と走らせた思想を今明晰に思い出せないのが残念だ。ひとつ思い出したのは、サックスの運指の指の動き(フォルム)を頭のなかで実際に映像として動かしながら書いた。そうだ。そのシーンだけはやけに鮮明に思い出せる。
2月
冒頭文 プロトコックス(福島)
これを書いたときのことをまったく覚えていない。何故だろう。ただ作品の強度は高い。変容では自分たちが書いていながら誰が書いたのかわからないような錯覚が起こる(福島さんともその点は意見が一致しているからおそらくそういう特徴を備えた作品でもあるのだろう)けれどここまでの作品はない。まるで覚えがない。唯一最後の小節は微かに覚えがあるけれど、それもほんの微かであり、、、この月は思い返すと月初めに東京六本木で文化庁メディア芸術祭関連のイヴェントに福島さんとともに出演した。だから福島さんの動機も14日に送られてきていて、幾分遅い部類のはじまりだったと楽譜で読み取れる。fineにいたる箇所を見てみる。自分は一度15小節目で終わろうとしている痕跡があり、それを福島さんが拒否して17小節目が送られてきている。今書いていて、なるほどこういう総括文の書き方もあるんだなと思った。楽譜には日付と時間が書かれてあり、ブログなどを参照すればもっと広がりのある文章がかけるだろう。そうするには相当な時間の余裕とそれに臨むよほどの覚悟めいたものがないと無理だけれどそういうことも頭の隅に留めておいても良い。(福島さんの文章はわりとそういうところにも注意をはらって書かれてあるようだ。自分はほとんど譜面しか見ない。総括文を書く時は)
3月
冒頭文 discontinuous music(濱地)
文字通り動機は不連続な音楽を標榜して書き始めたはずだけれど、今確認すると、すくなくとも動機に限って言えば弱いように思う。ある種の鋭利な、ソリッドな切り口をこの時提示できたとしたら展開はもう少し違ったかたちに(それは動機が違えばまったく作品が違ったものになるのはあたりまえの話なのだが)なったであろうが前半から中盤にかけては同じようなトーンが続く。(ただし4小節目、5小節目は別にして)それでも福島さんの小気味良いピアノにたすけられて部分部分はなんとか冒頭文の概念に寄り添おうとしているようにも感じられる。意図的にジャズの文脈のフレーズを所々挿入している形跡もあるが、明確な不連続性を表出するには至っていない。24小節目からの展開は気に入っている。切り口が鮮やかに見える。こういったコントラストが鮮明に浮かび上がる瞬間が前半から中盤にかけてもうひとつ、ふたつブロックを形成していたら、、、と思わずにいられないが、それでも全体を俯瞰してみれば冒頭文との乖離はあるけれど何かを留めているようにも思う。おそらく24小節目からfineに至るまで、それがそういう心象をつれてくるのだと思う。こういう冒頭文(概念)の設定は難しいのかもしれないと今(2015年2月24日)思い始めてもいる。
4月
冒頭文 立花の調律から(福島)
冒頭文は福島さんによる。自分の組織について言うと前半5小節目からの変化に問題があるように思う。今見ると違った方向性があったはずだ。そのため8小節目からの組織にも凡庸さが露呈している。随分迷って書いている。福島さんのきらびやかな組織だけが目を引く。自分はその後様々に変化の仕掛けを仕込んでいるが福島さんの組織に対してうまく機能しているとは見えない。11小節目に至ってようやくなんとかある種の方向性を見いだしているように見える。それがおそらく影響してか13小節目からの展開からはあらゆる選択の迷いは消えて思考がぴったりおさまっているように音楽は響きはじめる。fineに至るそれらの動きは明晰な互いの意識と響きが調和しているように感じる。ある見方をすれば5小節目から10小節目の自分のとりとめのない思考停止的組織がなければそれもなかったということだが、《変容の対象》という作品の作曲上起こる性質のひとつを如実に表出しているという意味に於いても興味深い作品になった。
5月
冒頭文 point_etude(濱地)
自分の組織の書式は当時書いていて今も未完の《elder》という作品の方式を模倣して書かれている。2014年の4月あたりから《elder》の書き換え書式を書いていてこの書式はサックスとコンピュータの室内楽作品《分断する旋律のむこうにうかぶオフィーリアの肖像。その死に顔》の書式とも同じであり、少し説明をすると、どちらも予め自身によって書かれたオリジナルのスコアがあり、そのスコアをもとに音価の変更、休符の変更、挿入、オクターブの変換操作などを施して組織を再構成するというもの。(オフィーリアの方は2014年の初頭に六本木のsuper deluxeの文化庁メディア芸術祭のイベントの際に福島さんとともに初演をしている)先に模倣と書いたが、この変容の5月の場合は当然オリジナルのスコアがあって書かれたものではなく、《elder》の音組織の組み方を模倣して書かれているという以外に共通点はない。ここは根本的に違うものなので別物でもあるのだけれど、同時期に書いていた、、、ここは意図的だった、、、2つの作品をいつか並べてみたいところだけれど、《elder》の方はまだunfinishの状態だ。ちなみに《elder》のオリジナルは《elder allegro》という作品。演奏されることは限りなくゼロに近いが、譜面は存在する。話は逸れたけれど結局自分の内部に於いてはそういうサイドストーリーや文脈の背景をどこかに関連付けてこうして作品の表面には直接現れるものではないにしても忍ばせることはよくやることで、ひとつここに書けたことはこういう機会でもないかぎり表白しようもないので総括文の機能ということだろう。音の組織は難解で規則性もなく、演奏する際には相当困難な組織が延々続く。「記憶されることを拒む組織」ということも重要な組織形成要素として書かれている。書いている当時で印象に強く残っているのは休符の存在がやたら気になったことだ。前半から中盤は特に8分音符で埋め尽くされた方が良かったと当時は思っていて、休符をいれて福島さんに送ってしまった後ひどく後悔したことを思い出す。5小節目の最後に現れる8分休符2つ。今確認してみるとまったくなんの問題もないように見えるが当時はやたら気になって福島さんにも確かメールでつらつら後悔の念を言ったようにも思う。慚愧の念と言っても良いほどに。12小節目からは普通に休符も使用されるようになってゆくが、その小節を書く前の自分の意識はいつまでも5小節目の休符は入れるべきではなかったということに支配されていた。つまり11小節目までそういった心理に居たということははっきり覚えている。今思うとどうしてあんな想念に支配されていたのかまったく理解が出来ない。自分のことなんだけれど。12小節目以降、休符はむしろ作品を豊かに彩っているように見える。福島さんの組織も端正に配置されている。自分の組織に於いて18小節目にこの作品唯一の4分音符が置かれている。As音。そして唐突にfineがおとずれている。
6月
冒頭文 反射光のアダージョ/Catoptric Adagio(福島)
冒頭文は福島さんによる。反射光と聞いてイメージするのはやわらかい日差しの午後、たゆたう時間、窓辺にゆれる薄い白いヴェールのやわらかなカーテンのむこうに顔ははっきりとはわからないが女性の姿が見える、、、というようなシーンと言えば幾分感傷的にすぎるかもしれないけれど、男ならそういう存在、想念上の架空の女性像を心のどこかにもっているものだ。そして何かの奇蹟が起きてそれに出会わないかと本気で願ってもいるが、それが決して果たされないのも知っているというような。あるいは、光の飛沫がレンズを反射して多層な色彩を描いているというような映像も浮かぶかもしれない。時間感覚はその時失われている。一瞬ではあるが、「永遠」をその時感じるかもしれない。詩がうまれる時はそんな瞬間ではないか。(数多書かれているように)。福島さんの組織の隙間をぬって旋律を配置する。そういう書き方をしたと思う。ある瞬間(つまりある音符のポイントで)その像が結ばれる。音の像。そういう配置だ。
7月
冒頭文 cutting up(濱地)
う~ん。どうもうまくいっていない。冒頭文の設定が変容にとって新しいものではないのも原因かもしれない。こういう方向性は過去幾度か試みてきたけれど、もともと変容の対象の作曲法がこういうことを含んでいるから、もっと突出して際立ったcut upが見えなければいけない。もしくはcutting upという概念がなるほど、こういう断面で見えるのか、、、というようなそんな構造体でなければ。3月の冒頭文といい、この種の概念は折を見て挑戦したくなるけれどほぼ敗北する。少なくとも自分の印象としては。
8月
冒頭文 輪生の声(福島)
そもそも自分の組織が福島さんの第1動機に相応しい組織だったか甚だ疑問だ。それが原因でもあると思うがその後の展開も精彩を書くものが続く。
9月
冒頭文 tonic incident II(濱地)
tonic incident IIとあるのはtonic incidentというimproviationのシステムをその当時考えていて、その方法をここでは採用している。けれど、旋律の組成はあまりうまくいっていない。サックスを実際に操りmode連結を高速で操作するこういった演奏は脳と身体の連結の危うい関係性を常に孕みながら正確に演奏されようとする重力が身体の内部で常にはたらいて演奏される。出力される音も実際スリリングだ。一方そういった身体性の発露(随分凡庸な表現でほんとうに嫌になってくるけれど)や、サックスの固有の音を介在しない状態(頭では鳴っているにしても)、つまり音符を書くという行為でそれをするとなると「とたんに」精彩を欠くのは何故か?というようなことを考えたような記憶がある。その後そのimprovisationシステムも途中で書くのをやめてしまっているということからも、そもそもそれ自体に強度がなかったのかもしれないが、これを書いていた時は変容でそういうことを試みたいと思っていたということは確かだ。
冒頭文harmonic incident(濱地)
9月は実はもうひとつ我々は作品を書いている。僕が福島さんにお願いするかたちで。それはサクソフォン・ソロの為の作品で、それを変容の形式、書式でかいてみませんか、、、というものだった。自分としては単純に福島さんが書く単旋律の無伴奏ソロの組織の姿(双晶という作品はあるけれど)を見てみたかったのと、《変容の対象》が亜種をうむとしたらまずはサクソフォン・ソロはそれに相応しいと思ったからだ。《変容の対象》は自分たちで演奏は想定しないが、密やかに自分だけで演奏をすることはこの場合可能なわけで、そういったことも少しは頭にあった。福島さんはこの9月は2つかかえて大変だったと後に語っていた。譜面を見ると福島さんがあまり書かない類いの旋律を書いている。それはやはり変容だからで、それ以前の組織が如実に機能、あるいは影響をその後の小節に与える、、、つまり別の作曲者が書くという、、、この作品の場合、別の楽器(普段はピアノ、サックスと別れている)ではなく、同じ五線上にある同じ楽器の組織を書く。という構造なのでオリジナルの変容では起こらないことが起こり得ると言うことも言えるだろう。
10月
冒頭文 in vitro(福島)
福島さんの動機に対する自分の視点は2拍3連による組織の執拗な使用によるある種の歪みの表出で、今、全体を俯瞰して見るとそういう態度を最後まで貫いてみても良かったかもしれない。中盤からの組織の変化はある決まった音楽言語の方向へ自らすり寄っていっている箇所も複数あり、何故そのようなことをしたのか自分で理解に苦しむ。最悪。曲の最後にin vitroの文字がそれまでより強く自分の内部に浮かんで同音の連続による組織を書いているけれど、中盤の自身の組織のそれは、前述のはっきりとした誤りの箇所と、ぎりぎりそうではない箇所を行ったり来たりしているという中途半端な現象(自身の思考の動き)を映していて、今見ると不快ですらある。
11月
冒頭文 For Deep End(濱地)
動機はサックスの練習中に書いたメモから。勿論予め変容のために前からストックしていたというものではなく、11月が始まってからの練習中に変容のためにとメモしたという意味だ。「深淵の為に」。冒頭文はJ.G.Ballardの短編小説を読んだ時に原題にその文字があって、深淵というのは例えば「深淵に触れる」とか、、、音楽体験でこういうのがある、、、素晴らしい演奏家による信じられないような演奏、それが付帯する《時間》に触れる時が、、、まさしくそれだ、、、そういう体験、あるいはそういうことを演奏という行為によって可能足らしめる演奏家自身の言葉も自分の記憶のどこかにあったのだろうか。とにかく深淵という概念は常に自分のなかにあるのは確かで、その概念を標榜した動機と言える。3小節目の中盤から音符の動きが激しく密度の高いものに変ずるが、福島さんの組織がその転換をあまり意識させない機能をもたらしているけれど、自分の焦点はすでにそれまでとそれ以降では違っていて、そこで一端終わって始まっている。つまり思考の断絶がそこで起こっているわけだ。また、10小節目からも断絶が起こっている。11小節目を書いた時その後の12小節目に自分が書く予定のことを福島さんに予め予告しておいたのを覚えている。11小節目に書かれた休符と8分音符によって隔てられた3連譜を繋げて書くというものだった。12小節目の福島さんが書いた総音価がその3連譜を順に繋げた総音価と同じだったから福島さんに(あらかじめ予告していたから)そういう意図で書いたのか後に聞いたけれどそうではなく偶然そうなっただけらしい。こういった予告は変容ではほとんどしない。作曲の構造上理由はあきらかだ。何故この作品に於いてはそうしたのか判然としないが、記憶にははっきり残っているから何か必然を感じたのだと思う。言語化はできない領域だけれど。1小節目、6小節目、最後の小節に同じ音形が刻まれている。
12月
冒頭文 in vivo(福島)
福島さんの動機にうまく自分は応えられていない。こういう現象もこの変容では避け難く起こる事のひとつだ。書いている当時はそれでもどうにか焦点を結ぼうとしてある種の確信をもって書いているには違いないけれどこうして改めて確認するとその過誤が否応なくこちらに提示されているのを見るしかない。結局作品の最後までその過誤が続いてfineで結ばれた。あっという間に。
2015年1月29日午前3時19分
和歌山県田辺市にて記す。(その後2月14日、2月24日、28日加筆修正)
濱地潤一
《変容の対象》2014年版総括
《変容の対象》2014年版総括文
2014年は個人作の発表自体は少なく、結局個人作品としての新曲の作曲は行わなかった。一方でMimizとしての演奏機会が1年間で3回あったことはうれしい出来事だった。コンピュータを介した即興演奏に向う時間は特別なものだ。演奏中にすべてを捉えることは難しいものの、偶然か必然か曖昧な領域でいくつかの要素が関係し、何かしらの意味が響きあうことがある。個人作品の発表としては2014年2月6日に六本木のSuper Deluxeで《patrinia yellow》のAltoSaxophone用に改訂したものを初演した。AltoSaxophoneの演奏は濱地潤一さん。また、同日に演奏した濱地潤一さん作曲の《分断する旋律のむこうにうかぶオフィーリアの肖像。その死に顔》という作品の初演は印象的だった。結局それ以外の作曲作品発表は行っていない。クラリネットとコンピュータのためのオリジナル版《patrinia yellow》(2013)の楽譜作成は2013年暮れから初めて約8ヶ月費やした。時間はかかったが丁寧に作成できたとは感じている。その他、各地に足を運んで様々な作家の作品に触れることの多かった年だった。そのような中の《変容の対象》2014年版の作曲であった。
《変容の対象》2014年01月 "neuroballet-hardcore"
冒頭文と最初の動機は濱地潤一さんによる。冒頭の動機の印象は2013年版の12月と類似する世界感を感じたのを記憶している。ピアノは中盤までの三連譜のリズム動機が印象的に支配する。その派生と考えられる非周期の和声群が後半続くが終わり方は濱地さんと福島とで印象が異なったようだ。濱地さんは「unfinished fineのようなfine」と語った。
《変容の対象》2014年02月 "プロトコックス (Protococcus nivalis)"
冒頭文と最初の動機は福島諭による。1818年北極探索中の英国海軍中佐ジョン・ロスがグリーンランド北西部で発見した赤雪の現象に対して、長い間それが何ものであるか答えが出なかったという。雪氷藻類という微生物であり、紅藻ではなく緑藻の仲間であることが判明し、最終的に藻類学者ウィレによって学名Chlamydomonas nivalisとなったのは20世紀に入ってからであった。その前に、スウェーデンの植物学者アガードがこの藻類につけていた学名がでProtococcus nivalisある。ファーブル植物記を読むと、この赤雪の現象はアガードが名付けたプロトコックスという名で紹介されている。未知なる対象そのものは変わることはないが、名付ける名前自体は必要があれば変更されていくこと、あるいはこうして時代の狭間に取り残される名前が存在すること自体に不思議な感覚を覚えた。人類の知の集積の、その変動の有り様を動的なものとして意識させられた気がしたからだろうか。楽曲にはやや不安が忍んでいるようにも思うが場面の移り変わりには比較的自由な流れが感じられる。
《変容の対象》2014年03月 "Discontinuous music"
冒頭文と最初の動機は濱地潤一さんによる。メールでは冒頭文の意味は「不連続な音楽」という意味です、と書かれていた。冒頭文の意味するところは実は音楽においては非常に難しい問題を含んでいる。音楽は通常、実時間のリニアな流れの中に展開されるものであり、時間の流れ自体は揺るぐことなく連続的であるからだ。この問題に際しては《変容の対象》2012年02月の"常に多様で印象的な動機を多く収集すること。そのために起こる前後の断絶について。"の際に意識した観点とどこか繋がるようにも感じられた。言葉が指し示す地点とどうも音楽が結びにくい性質を持っているのだ。ここでもやはりpianoは具体的な解決方法を知らないまま進んでいく。途中、終止感の感じられる箇所を何度か経験するも結局30小節まで音は並んだ。終止の見つけ方はこの月は丁寧に扱えたようで両者納得のものとなった。2014年01月の終止方法と形としては似ているかもしれないが、内容的には対称的であった。しかし、それが何に起因するのか今はうまく説明できない。
《変容の対象》2014年04月 ""六花(りっか)の調律" から"
冒頭文と最初の動機は福島諭による。[cis,e,fis,gis,ais,h]の6音を最初の和音とし、一音ずつ変化させて2種類の和音の構成関係を交互に変化させながら、やがて最初の和音に戻るという進行を考えている。結果的に12種類の和音を巡ることになる。ピアノは1小節につきひとつの和音を対応させている。濱地潤一さんへはこのことは事前に伝えてはいない。しかし、9小節目を書く際に「和音は互いに1音ずつの変化で進行し、表と裏の形をとりながらそれぞれ6種類合計12種類の形を巡る。(ここで9種類目)」とメモを楽譜中に添えている。12という数は予告なしに使われる数としては長いものだろうという気持ちからだったと思う。13小節目以降のピアノはアルペジオを放棄するが、和音の進行は同じ経路で循環する。25小節目からは12種類の和音が再びアルペジオの形となって吐き出されて終止する。
《変容の対象》2014年05月 "point_etude"
冒頭文と最初の動機は濱地潤一さんによる。最初の動機を受け取ってから返信するまで4日ほどかかっている。それまでに構造的な分析を一応は試みていた。
「濱地潤一さんからの1小節目の分析、低音と高音のセットを考えると八分音符の拍のまとまりで以下のような数列が見える。類似した箇所で行を変えると最後の2拍と3拍が違うだけのリズムが伺える。
4 3 3 2 3 2
4 3 3 2 3 3
などというメモが残っている。ただ、結局こうした分析は具体的な方針に影響は与えるほどではなかった。冒頭文の印象を受けてpianoも単音を不規則なリズムと共に紡いで行くようなアプローチになっている。同じ瞬間に2音以上が鳴ることがないから、Alto Saxophoneの動機に準じた姿勢を貫いている。途中、濱地さんは2小節目でfineでも良いかもしれないとメールで発言されていた。5小節目のAlto Saxophoneは小節の最後に四分音符1拍分の休符が入るが、これは濱地さんのミスだった(意図したものではなかった)と言う。実質的にはこの休符がひとつの転換点となり、6小節目から11小節目までがもうひとつのブロックになった。おそらく11小節目の休符は5小節目を受けて意図的な休符であったろうと推測する。12小節目のpianoは冒頭のpianoと同じものが使われている。濱地さんは別のアプローチを選んでいる。最終的には3つのブロックに分けられる楽曲となった。
《変容の対象》2014年06月 "反射光のアダージョ/Catoptric Adagio (四分音符 = 40)"
冒頭文と最初の動機は福島諭による。どこか気怠い印象を持つ楽曲でその印象はどこまでも続いていく。途中、これは冗長なものになっていまいか、という迷いを濱地さんへ連絡してもいる。実際、5分30秒を超える長さを持ち、2014年版の組曲の中では最も長尺な曲となった。最初のpianoの動機は実家で何気なく弾いた響きの印象を採用している。作曲中もpianoの鍵盤の配置を頭に浮かべながら音を配していた。日々の生活の中でふと巡りあった印象と約一ヶ月向き合わなければいけないという大変さがあった。大きな転調も無く、機能も不明瞭な響きを持つ。終盤はどこで終止させるか迷いながらもうまく抗えなかった。両者とも、後半は所々極端に短い小節を挿入したりもしている。18小節目にようやくその終結点を見つけることができた。
わずかに関係するかもしれない要因として体調のことがある。毎年6月頃は体調を崩しているが、2014年も軽い風邪をひいた。
《変容の対象》2014年07月 "cutting up"
冒頭文と最初の動機は濱地潤一さんによる。冒頭文を受けて音楽におけるカット・アップの印象をどうするか、そのようなことを漠然と考えていた。2014年3月での"Discontinuous music"(「不連続な音楽」)との違いなども意識された。12小節目のAltoSaxphoneの旋律はオーネット・コールマンの旋律の引用が持ち込まれている。実時間の中で切断され持ち出された音楽的な要素を意識するためにはどうすればいいのか。この頃の私には、それは一部を採取し再構成し続けることのように思われた。16小節目までに現れたpianoの要素を17小節目以降はできるだけ多く再出現させることに注意を払った。楽譜にはfrom[(小節番号)]という形で引用元のメモを残してある。そのためか、楽曲の後半は印象が前に進まないある種の閉じられた世界をpianoパートは持つことになったようだ。AltoSaxphoneパートはそれとは異なる動きを持っているために独特の質感を得ている。
《変容の対象》2014年08月 "輪生の声"
冒頭文と最初の動機は福島諭による。植物の葉の着き方には「互生(ごせい)」「対生(たいせい)」「輪生(りんせい)」等があるという。この頃、機能和声の転調について見直していた。pianoの和声はシステマチックに組んでいる。pianoとAltoSaxophoneの旋律が近づいたり離れたりする中間部までは《変容の対象》らしいスタイルになった。13-15小節が中間部というような形になったが、16小節目から終りまでは冒頭の印象の展開という形であろう。
8月の終わりにはサントリーホールでシュトックハウゼンと三輪眞弘氏の作品が演奏されるコンサートがあり、足を運んだ。三輪眞弘 “59049年カウンター ー2人の詠人、10人の桁人と音具を奏でる 傍観者たちのためのー"に強い衝撃を受けた。
《変容の対象》2014年09月 "tonic incident II"
9月は濱地潤一さんからの提案でふたつのバージョンの《変容の対象》を同じ時期に作曲することとなった。2曲とも冒頭文と最初の動機は濱地潤一さんによる。最初のメールでは「incidentは出来事。tonic上で起こる出来事。ハーモニー上で起こる出来事。そういう概念です。今月は。」
と添えられていた。
冒頭文"tonic incident II"はpianoとAltoSaxophoneの通常の形態を想定された楽曲である。濱地潤一さんからの説明によると"tonic incident"のIは濱地潤一さんのSaxophoneソロを想定した曲で既に存在するとのことだった。楽曲は即興を前提としたシステムをもっており、それと同様のシステムをこの"tonic incident II"でも採用しているという。pianoのアプローチには制約はなかったが、返信には5日程度を必要とした。Saxophoneは"高速に移動するシンプルな音階の変化によって移ろう音響効果"にフォーカスしているということは伺っていたのだが、pianoにはそれを借用したアプローチはできなかった。中盤まではpianoも機能的な変化も比較的身軽に行っているものの、終盤に向けてはほぼ単一の響きの中に留まっている。そうすることでようやく終結点を見つけているようにも思われる。
《変容の対象》2014年09月 ver.SS "harmony incident"
冒頭文"harmony incident"はAltoSaxophoneのソロのために作曲されている。作曲の仕方は第1小節目が濱地潤一さんからのもので、2小節目は福島諭が、3小節目は濱地潤一さん、、と交互に繋いで行った。単音楽器のソロ曲でありながら、"harmony incident"と名付けられていることに留意しひとつ前の濱地潤一さんの小節に対して留まっている和声感、響きの印象を意識化してそれに対して展開(どのような方向性でもいい)させる和音を選択することに注意を払った。そこで選ばれた音だけを使用して1小節を構成する、そのようなやり方を貫いた。楽譜には選んだ和音をメモしておくようにしてある。楽曲の終わり方は普段の《変容の対象》で行っているようにはいかなかった。続けようと思えば続けられる、という可能性が広いように思われた。結局、月の終わりの残り時間と現状を照らし合わせながらの作業になり、濱地さんと私の中で納得できる地点を探った。
ふたつの《変容の対象》を進めるというのは思っていたよりも大変なことであった。おそらく1月に2つが最大、3つは無理であろうという気はしている。
※9月中旬には映像作家・池田泰教氏の「3Portraits and JuneNight 」が東京で上映会があり足を運んだ。作品にはAmorphousRingIが一部使用されており、シアターで聴くといっそう物質的な質感が増したように思い、濱地潤一さんへ報告したりした。また、下旬には映像作家・前田真二郎氏の『日々”hibi”AUG 7 years mix [2008-2014]』の上映会が岐阜県美術館で行われ足を運んだ。この作品の中でも濱地潤一さんのSopranoSaxophoneの音色が聴けた。久しぶりに聴く曲の断片もあり新鮮に感じた。また、前田真二郎氏の『日々”hibi”』のシリーズは12年でひと区切りと決められており、その意味ではまだ完成しているわけではないが、撮影行為が12年間の8月を集積することに特に意識的であるように感じられた。《変容の対象》もルールと日々のドキュメントを含んだ作曲行為として、映像作品『日々”hibi”』からの影響もあるように感じているが、未来からのある地点を想定して現在に焦点を当てるような行為などというものが、撮影行為には可能であっても、音楽には可能なのかどうかを考えさせられた。撮影行為にあって作曲行為にないもの(あるいはその逆)、そのあたりは今後突き詰めていきたい課題となった。
この岐阜の上映会には濱地潤一さんも招かれており、ふたつの《変容の対象》の作曲作業が続く中、印象的な時間となった。深夜には《変容の対象》の確認を少しだけしもした。結局、実際に会っている間に書き進めるようなことはしなかったが、最新の段階を濱地さんが聴いた後に「なるほど」と言われた時の印象はよく覚えている。現在の形を聴いて頭の中に次の可能性がよぎるような感覚は私も何度と無く経験しているが、その様子が濱地さんの中でも起こっているように感じられたからだ。
《変容の対象》2014年10月 "in vitro"
冒頭文と最初の動機は福島諭による。in vitroは分子生物学の実験などにおいて使われる言葉でもある。語源はラテン語で「ガラスの中で」、意味は「試験管内で」(ウィキペディアより)ということらしい。pianoの第一動機は単純な響きによって構成されており冒頭文との直接的な繋がりはあまり感じられない。濱地潤一さんも返答に苦労したと言っていたように思う。楽曲は9小節目にpianoの冒頭が戻りそこから動きを得るように感じられる。終盤はSaxophoneの動きが停止(3小節分に渡るGの連続音)、続いてpianoもその停止を受け継いで終曲する。どこか「動きの衰退」というものも想起する小品となった。
《変容の対象》2014年11月 "For deep end. "
冒頭文と最初の動機は濱地潤一さんによる。「深淵のために」という冒頭文と、休符が多く印象的な形を持つ濱地さんからの第一動機を受けて返信するまでに1週間ほど時間をかけている。もう忘れてしまったが最初動機を聴いた時に試したいアプローチが頭にひとつ浮かんだ。しかし、結局それは形にはならなかったように記憶している。中旬過ぎに名古屋でMimizの本番があったこともあり、この月は上手く《変容の対象》に向えていない様子が当時のメールから伺える。
実際のpianoのアプローチでは、最初から和音の変化を記録してあった。3小節目の途中からと6小節目にはpianoの和音は最初のものに戻って三たび続けられている。途中で立ち戻り、そしてそこから新たに展開させる場合は展開させるというアプローチになった。終わりには濱地潤一さんが冒頭のフレーズを回帰させている。終曲した後のメールで「最後や、途中で動機を繰り返し登場させるのは変容では意識して避けているのであまり気がすすまなかったのですが、」と書かれており、普段の濱地潤一さんの態度が伺えた。今作では特に意識的にあえて使用したということだろう。結果は悪くないと感じている。
《変容の対象》2014年12月 "In vivo"
冒頭文と最初の動機は福島諭による。in vivoは分子生物学の実験などにおいて使われる言葉で、2014年10月に使用したin vitroと対になる言葉でもある。意味は「生体内で」。pianoは左手の低音のリズム動機と右手の和音的なアプローチというスタイルを貫いた。AltoSaxophoneは音数は少ないが要所で効果的なアプローチを終始続けている。徐々に熱量が高まるような感じで終結しているが、これは冒頭文をIn vivoと名付けた段階で予測した範囲内の出来事であった。しかし、どうそれが実現されるかは別の次元の話であり、実際には比較的少ない要素の組み合わせとそのバリエーションでどのように変化するかを確かめながら進めることができ有意義だった。pianoの和音は1小節毎に変化させている。途中での回帰はなく、流れに任せた22種類の和音が繋がれていることになる。書き出すまでに時間がかかったが、11月とは対称的にその後は自分自身の作曲時間も多く取れた月であったから分量的にも他より極端に短くはない。印象的な1曲になった。
2014年12月31日から2015年1月1日新潟にて。
(2015年2月21日第一回推敲)
福島諭