+ 《変容の対象》2016年版
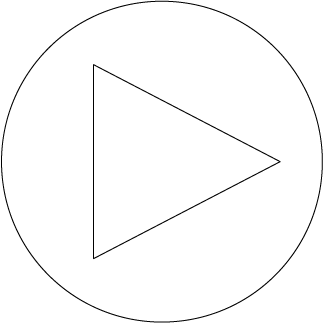 00:00 [00:00]
00:00 [00:00]
作曲: 濱地潤一 + 福島諭
《変容の対象》2016年版総括文
2016年は良い発表の機会が2つあった。一つは映像作家・前田真二郎監督作品のライヴ上映のための音楽に津上研太さんとコンポジションし演奏した目黒の庭園美術館での発表。
もう一つは新潟での2016年最後の演奏で2つの重要な作品を演奏した。
1つは福島諭さんに委嘱したサクソフォン・ソロ《双晶I》
1つはサクソフォンとコンピュータのための室内楽シリーズの新作《respice finem》
1月[冒頭文]無し(冒頭文:濱地)
27小節にわたっての循環呼吸奏法による組織を書いている。書いている、、、と、書いたのはもうすでにそのことを忘れているからであり、どうやってfineを迎えたかも確認した時にはわからなかった。忘れているというのは昨年も書いたはずだ。忘れる能力ということも人間の記憶のシステムの中に組み込まれているらしいが、こうもすっぽり忘れているのはちょっと意外だった。ただ循環呼吸奏法に関しては明確に定義してることがあって、それは長く思索してきた概念であり、それがようやく明確なヴィジョンと、ある種の普遍性を自身の内部で獲得できたのがようやくこの数年のことであり、その概念を変容に書く場合は常にそれを機能させることを想定して書いている。
2月endophytes(福島)
Jazz saxophoneの手法を引用したもの。全編それで書かれている。クラシックの領域においてJazzのソリッドな例えばcharlie parkerの「あの感じ」、、、あの感じとしか言いようのないアウラを表現するのはほとんど絶望的に困難であるのは、それが本質的に「演奏されたもの」と「譜面というメディアに書かれた」ものといういわば全く別の領域に属するものである限り成功している例はほとんど無い。私の知る限りにおいて。そもそもそれは別の領域に属するものだ。
自分がこう言った組織を書く場合、あのアウラを表出するために書いているのではなく、先述した引用という行為に焦点がある場合に限る。今作品もそうで、Jazzというサックスの技法においてクラシックの文脈とは別に、そこに肥大し発展した技法をコラージュする。といったような概念上の興味はまさしく譜面というメディアに書かれる、、、という行為の時間創出の上ではその意味を複合的に持ちうる。そこが問題なのであって、実際に演奏されるかどうかは問題ではない。というほどの乖離があるのだ。
3月Accept(濱地)
どうにも名状しがたいけれど気に入った作品。ソプラノサックスの音高のレンジ、同音の連続挿入の組織など多分その時の興味が反映されているような譜面に見える。実際こう言った組織形成は例えば感覚的に出てくることはない。10~13小節目の福島さんの組織も見事だ。こんな組織間の攻防はさて、実際のリアルタイムのインプロヴィゼーションで表出するだろうか。譜面上でこそ起こる、謂わば概念の表出故の組織構造体に見えて興味深いが、おそらくこのレヴェルに至るには変容の数年の時間経過なくしては現れなかったようにも思える。
4月Loop,Clip(福島)
冒頭文のLoop, Clipという指示に支配されて書いているはずだが、時間をおいて今、改めて確認してもおそらくその視点、あるいは焦点が変遷を繰り返しているので判別は露骨な場合を除いて明確に取り出すことは難しい。ただ、こう言った簡潔な具体語の冒頭文の指示の良いところは楽想が硬質な質感を備えて組み上がっていくようで、変容ではいくつかその例を見ることができる。おそらくその具体的な言語指示を常に参照して書くので、ある種の「含み」を拡大解釈してまた新しい概念で組織を書くということができない。ということも関係している。もっと抽象的な冒頭文指示だとこちらの視点によっては「含み」を相当別の遠い距離の概念と結びつけることも可能で、そこに自由さが生まれるが、逆に冒頭文の指示領域から乖離して機能し始め結局冒頭文を無視して組み上がって行く組織というのも変容ではよく起こることだ。冒頭文のある作品と例えば2009年から数年は冒頭文がない時代(もはや時代と言っても良い。驚きだが)との差は、、、と考えさせられる。
5月self corrosion self erosion (自己侵食)(濱地)
一応冒頭文(自分が書いた)に沿って書かれているらしいが、まず自分の最初の動機が良くない。それが後々まで影響していて、だだ情報量の多いだけの組織が続いているだけといった印象だ。福島さんの組織によってある瞬間は目をひくものが立ち現れるが、全体としては散漫な印象だけが残る。冒頭文は悪くない。むしろ良いものだとは思うけれど最初が過誤の始まりであり、結局最後までうまく像が結ばれなかった。
6月Freeze out(福島)
自身の組織に関して言えば捉えどころがない。けれど面白くないというわけでもない。摑みどころのない印象もありながらそう悪くもない。どうも言及するのが難しい。
7月contortion(濱地)
自身の動機があまり明確に書けていないのか、原因はそこのあたりにあると思われるがはっきりとはわからないがどうも焦点が合わない。5、6、7月の総括文が言葉少なくなっているのは結局言語化するには材料が「言語側の領域」にとって少なすぎるというのもあるだろう。うまく言えない。端的に言えばそういう作品が続いている。
8月orangeade”starry sky”(福島)
福島さんによる冒頭文は一風変わったものだ。明確な判断をしないまま書いたように朧げに記憶している。自身の組織はいかにも自分が書きそうなもので、自分にとっては自然ではあるが、面白みに欠ける。作品はあっという間に終わる。何も起こらないまま終わったという感じでもなく、考える間もなく終わった感じがしている。
9月dead silence(濱地)
書くのは難しい。そこに留まっているものが何か、、、形而上では沈黙が美を内包することは信じることができる。
そして重要なのは、譜面というメディアに書かれているからこそ表出する世界というものがある。ということだろう。
10月monochromatic mosaics(福島)
変容の対象では当初冒頭文を参照して書いていてもそこにある眼前の音の意志によって冒頭文から離れて音が組織されていくこともままある。この月の作品も冒頭文のそれを参照しながらも音自体が導く導線によって書かれていく様相が見て取れるが、これは常に起こることで、それの力が強い場合は全く冒頭文が機能していない作品も結果できる。いうまでもなく人は言語で思考し、名付けることでその存在を「そこに在る」と認識できるが、音楽はその領域外のものを多く内包している。と、いうことを時として強く考えさせられる。
11月discours(濱地)
動機から冒頭文の概念を想定して書いたであろう組織が敷き詰められているように譜面を見た。全く(とここは書いておく)「情緒」によらない組織は潜在的に、あるいは常に「それ」を、他の作品においての演奏時にも標榜しているから自身にとって際立って目新しいことではないけれど、こういう組織の形成を目で追ってゆく時間、対峙する時間がある密度を持って迫ってくるのも事実だ。
12月polynomial(福島)
ずいぶん変わった感触の作品だと思った。書いている時間の周期の2小節間はそれぞれ明確に書いているとわかるがそれが連続した時間で繋がるとこういう様相を浮かび上がらせるというのは変容では起こるべくして起こるけれど、そういうのとも少し違う。そんな感触。
2017年1月から3月に記す。
濱地潤一
《変容の対象》2016年版総括
2016年は2015年の春に感じた予感の余波にあるような一年だった。予感についての考えを自分なりに深めたいと2015年に作曲した《春、十五葉》の楽譜の清書作業も続いていたし、いったい「予感」とは何であるのかと、長く問い続けた一年だった。考えるほどにこの短い問い自体の強度は強く、面白いと思う一方で、答えらしいものはいつまでたっても得られない何か途方もない感覚も受けた。結果的に「予感とは何か」という問い自体を問う1年となったのかもしれない。
2016年の中頃から後半はG.F.G.S.レーベルからのCD「福島諭: 室内楽2011-2015」が発売され、それに伴う発表を東京と新潟で行った。奏者の皆さんは各所から集まってくださり大変嬉しかった。東京では全て初演時のオリジナル・メンバーでの再演ができたという事実は大きい。また同時期に新潟で行われた文化庁メディア芸術祭新潟展の準備や発表にも追われ慌ただしく過ごすことになった。初めてのことも多く、反省やそれに伴う疲労感も味わったが次への糧としたいと感じている。新潟展のテーマは記録や記憶に関係することだったので、個人的には東日本大震災から5年以上の月日が流れたことに関心がいったのは必然だった。時間の経過に伴う作家それぞれの視点を意識する機会にもなった。自分自身は、まだ震災は終わってなどいない、と強く意識していたつもりだったはずだが、結果的には確実に記憶や何か身体感覚のような部分での抗えない変化、そして何か周りの意識としても確実に変化しているものがあると強く意識される結果になった。全く同じ状態で忘れずにいることなどできないのだと、ゆっくりと実感させられたようでもあった。その前提に立った上で、何をできるのかを考えていくべきなのかもしれない。
そんな中、濱地潤一さんとの《変容の対象》のやり取り自体はここ数年と大きく変わらないペースだったのではないかと思う。私の書くピアノ・パートに関しては徐々にシステマチックな作曲方法を使うことが減ってきたように思う。その時々の体調や許された時間に合わせて即興的にアプローチすることが多くなっていた。技巧面では演奏自体は不可能でないにしろ、難易度が高いと予想される楽曲も増えてきたとも感じた。これはこれまで《変容の対象》の実演の機会を得て、高いレベルの演奏者の方々と知り合ってきた事実とも無関係ではないだろう。
1月[ (冒頭文無し) ](circular breathing multiphonics 倍音操作は奏者の任意で行う)
この月は濱地潤一さんからの動機で始まり、冒頭文は無し。ただ、サクソフォンの演奏法についてのコメントが添えられていた。循環呼吸での演奏で、指使いの指定は楽譜に従うが倍音操作に関しては奏者の任意との指示なので、実際の演奏に際してはここWEB上でのサンプル音源とは著しく異なると想像される。
メールのやり取りを確認すると、楽譜上も14回と多めのやり取りをしているのは久しぶりということと、お互いの中でそれなりに新しい表現を模索できたという充実感のようなものがあったようだ。pianoの作曲に関しては作曲中はほとんど鍵盤を弾きながら音を確認して決定していたと書かれており、「後半は手癖も出てしまって、」というような事を書いているが、今はもうその作曲時の記憶はなくなってしまった。
濱地さんの旋律は常に一定のビートの中に周期を変えるアルペジオが自由な形で書かれていて、その律動に呼応するようにpianoはリズムと色彩的な響きを模索しているように聴こえる。永遠に続くかのようでもあるが少しずつ状態を変化させて突然にやってくるfine。その直前に一瞬バランスを崩すようなリズム組織は音楽的に機能していると思う。
この月はあえて実際の演奏では極めて困難であろう領域に踏み込んだ、という意識も互いに共有されていた。
2月[endophytes]
冒頭文は福島諭による。単語の意味は、endoはギリシャ語で「内側の」、phyteは「植物」の意味となる。植物の体内に共生する真菌や細菌などの微生物の総称とされる単語を採用した。植物自身と共生関係にある微生物との関係が植物自身の免疫機能と関わっているという構造が個人的には音楽的なイマジネーションを運んで来ていたのだと思う。ピアノに関してはいくつかの細かな動機が各所で自由に散りばめられている。作曲中、どのような意識で書いていたかはこの月もそれほど具体的に記憶には残っていない。冒頭文の単語はこの時期に植物関係の書籍を読んでいて気になったということで冒頭文に採用したのだと思う。メールを読み返すと、お互いに体調が悪い様子と、濱地さんはEric Dolphyの組織法を研究中で、5-6小節目は完全に「それ」を採用していると書かれている。
2015年に福島が作曲した合唱曲《Eupatorium Fortunei》の録音や、久しぶりにMimizでの本番の録音を濱地さんへ送って聴いて頂き、意見交換を行っていた。勿論、そうしたやり取りと《変容の対象》とは直接的な関係は無いのであろうが。
3月[Accept]
冒頭文は濱地潤一さんからのもの。10小節目からピアノはそれまでのアプローチを離れる。それを起点として新たな展開を得て行き来し、終盤はサクソフォンとピアノの音型の溶け込むような領域に接近している。そしてさらに大きなうねりを生むかのような刹那離散して終わる。冒頭文の関係もあるのか、サクソフォンとピアノは通常よりも親和性を目指しているように、(曲想として常にそうなっているかは別の問題であるが、)少なくとも方向性のベクトルとしては親和を目指しているようにも聴こえる。ただ、《変容の対象》においては明確な協調だけでは推進力も生まないということも経験的に分かっているため、停滞しないための上手い間合いを保ちつつ作曲は行われていたのではないかとも思われる。しかし、やり取りはこれまでの積み重ねで得られた経験則の範囲内で淡々と行われているようにも思う。
この月は濱地潤一さんは映像作家の前田真二郎さんの関係の発表を、福島は新潟でゾンビ音楽の安野太郎くんの発表に新潟の作家と共作し発表するというような事をお互いに行った月だった。《変容の対象》でのやり取りしているソフトウエアのバージョン変更作業なども行っていて慌ただしいが、この月の《変容の対象》についてはお互いに何か言葉を交わすことなく音のみでやり取りを進めていた。
4月[Loop, Clip]
冒頭文は福島諭からによる。第1小節目を送った最初のメールでは「新潟は桜が咲き始めました。」とある。個人的にこの月の下旬では周りの大切な方が亡くなった事もあり、環境的にも精神的にも大きな喪失感を感じていた。携帯もこの月に壊れた。《変容の対象》自体はそうした状況の影響はないと思えるが、冒頭文からの印象は受けてかなり断片化されている印象を受ける。終わり方は珍しい方法が使われていて、一瞬過去の印象が浮かび上がって終わるような仕掛けになっているが、このままで良いかの判断を大分迷った事は記憶している。
《春、十五葉》('15)の楽譜の清書が一応一通り終わった頃でもあった。
5月[自己侵食 / self corrosion / self erosion]
冒頭文は濱地潤一さんからのもの。やり取りは12往復半なのでこの頃の平均的だと言えるが作品自体の重量感はある。ピアノも重厚な響きが多用されている。転調や色彩的な意味ではそれほど変化は無いが、終盤の響きの固まりによるリズミックなアプローチはこれまであまり見られなかった表現領域かもしれない。
この頃《春、十五葉》について改めて考えていて、「予感」について調べたいと思いながら行き着いたのはキルケゴールだった。何年かぶりに「死にいたる病」を読み返したりしている。濱地潤一さんとも何度か話題にしてメールでやり取りをしていたが、キルケゴールに思考が入れ子になって閉ざされ続けてているような構造を見る、それは音楽的でもあると感じていた。
6月[freeze out]
冒頭文は福島諭による。冒頭文の印象を受けて、pianoのアプローチは意図的に任意の箇所で響きの連続を生むように組んでいる。結果的にはそれが打楽器的なアプローチとなって終盤に向かっている。音の積み上げ方などもこれまで使用してこなかったようなアプローチを採用しているため、これまでの《変容の対象》としても新鮮な領域を持ったものになっている。
メールではこの月もキルケゴールの話題をかなりやり取りしている。また、《春、十五葉》の録音音源を使ってリミックスするという事を濱地潤一さんとも進めており、その録音に際しては、濱地潤一さん自身はキルケゴールを読んだ事とも少し影響があったとも書かれていた。曰く「永遠を閉じ込める」意識、と。
7月[contortion]
冒頭文は濱地潤一さんによる。"contortion"は「ねじれ」「(顔などを)ゆがめること」などとある。音価が伸縮するようなサクソフォンの旋律に対してピアノも揺れを持たせるような組織になった。8小節目で一旦リズム的なズレがなくなるが、その後また自由に展開していく。最後はねじれが解けていくような印象もあり、一定の終止感があるが、どこで終わらせるかについては各人の意見は分かれていたようだ。メールでのやり取りを読み返すと、福島が終止のつもりで送ったものを、最初濱地さんは終止するつもりなく受け取り、考えた結果そこで終止させる、という経緯があった。結果的には同じ意見となったわけであるが、そこへ至る道筋は異なっていた、ということは面白く感じられた。
8月[orangeade "starry sky"]
冒頭文は福島諭による。なぜこのような冒頭文にしたかははっきりと覚えていないが、その日に何となく頭に残っていた、本来別々の要素を意識的に繋げて組んだように思う。第1小節目を送ったのが11日で、濱地さんからのそれに対する返答が15日だからスタートは早くない。そのためか楽曲全体はほぼひとつのアイディアのみで書かれていて大きく展開はしていない。冒頭の数小節の印象は新鮮な響きを持っていると感じる。
9月[Dead Silence]
冒頭文は濱地潤一さんによる。ここまでの比較的音数の多いアプローチに対して、極めて音数の少ない曲になっている。冒頭文と濱地潤一さんからの1小節目に提示された印象的なロングトーンの提示によって方向性のほとんどは示されているが、それに対するピアノのアプローチが正しかったかどうかにはやや疑問が残る。少なくとも冒頭のピアノの音数は多すぎたかもしれない。7小節目の「循環呼吸 / circular breathing」と指示のある箇所からはさらにピアノの音数も減り、音と無音のバランスがユニークなものになってくるが、それでももっと良いアプローチは有り得たかもしれない、と今では思う。
14小節目の最後のピアノの音(「h」)で突然訪れる断絶感は冒頭文との関係からも悪くない終始感はある。
10月[monochromatic mosaics]
冒頭文は福島諭による。冒頭のピアノの色彩感を考えると冒頭文との整合性はやや悪い気もするが、それも含めて分裂的な印象がある。13小節目のピアノの段階的な上昇から14小節目の断片的なフレーズに向かう箇所には小さなクライマックスが置かれるが、大きな展開はせず、この曲も音楽的なアイディアはほぼひとつでそのまま終始に向かう。
11月[discours]
冒頭文は濱地潤一さんによる。"discours"には「(真剣な)対話」「話法」などの意味があると思い[*1]、ピアノに関しては言葉のイントネーションなどを意識して組織していったと記憶している。故に、リズム的には右手と左手が分かれる部分は少なく、両手が揃って弾かれる箇所がほとんどとなった。11小節目後半のソプラノ・サクソフォンとのユニゾンは意図的なものだが、これは8小節目冒頭にユニゾンを匂わせる濱地さんからの組織があったことを受けてだと思う。ずっとそれぞれが好き勝手に言いたいことを言い続けているような曲にあって、ユニゾン部分は印象的な箇所になっている。
[*1: もともとの濱地潤一さんの意図は"フーコーなどにみられる批評用語としてのディスクール = 言説"という意識で使用したものだった、と後日伺った。上記のような作曲時における着眼点は福島側の誤認と言える。]
12月[polynomial]
冒頭文は福島諭による。"polynomial"は数式の「多項式」にあたる言葉であるが、冒頭のピアノには極めて叙情的な要素がある。一般的に無機質に感じられる数式などに対するイメージからは、冒頭文との関係は薄く感じられるかもしれないが、同時に個人的には函数とそこに代入される数値の構造的な関係性に叙情性が許されないということもないだろうとも感じている。実際に音楽におけるリアルタイム・サンプリングを援用したセッションにはそうした情緒的な結果も感じられるからである。ただ、こうした意識と、《変容の対象》の方法論にどれだけ同じようなことを含ませられるのかについては、未知である。詩的な領域以外には何も示せないかもしれない。ただし、この月のやり取りに関してはそれでも良いような気もしていた。最初から、ある種乱暴な要素の配置が試されているからである。
17小節目から19小節目の終止まで、濱地さんはソプラノ・サクソフォンの音を書かなかった。
2017年01月4日 ~ 2017年4月10日までに記す。(第1稿)
福島諭