+ 《変容の対象》2020年版
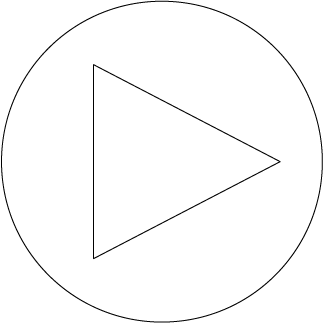 00:00 [00:00]
00:00 [00:00]
作曲: 濱地潤一 + 福島諭
《変容の対象》2020年版総括文
我々の2020年の最も重要な出来事ということで言えば、愛知県芸術劇場での映像作家・前田真二郎さんの作品「日々」と《変容の対象》との合同作品の初演が挙げられる。もうずいぶん前からこの作品の萌芽は芽吹いていたように記憶しているけれど、その作品が実際に動き始め、様々な過程を経て、そして初演を迎える、、、、名状し難い感情と感慨が付帯するそんな初演までの道程だった。それ以降は今の猛威をふるうコロナ禍のなか全ての演奏機会、発表機会がなくなり例外的に一度限定的な集まりのなか独奏で演奏したのみで未だに目処もつかない。(Jazzという音楽のフォーマットをモチーフとして、テナーサックスを演奏した。時間の乖離、断絶を内包した演奏ということになるけれど、そう言った概念がなければ僕は聴衆を前にしてjazzを演奏することは難しいと考えたからだ。いささかもったいぶった説明に留まるのだけれど、、、)
前田真二郎監督作品「日々」と我々の作品《変容の対象》は、長い時間継続し持続し続ける概念的な共通に近い運動を行っていて、それが両作品を結びつけている一つの大きな要素であり、まずはその視点からこの共同作品は始まっている。それを前田さんが映像送出を我々の五線譜で書かれたものから「読んで」送出するという形でサクソフォンとピアノと映像がアンサンブルするという形式をとり、つまり五線譜というメディアのもと映像と楽器が「合奏」する作品に導いた。ステージ上の三者はその楽譜によって「時間」を紡いでゆくわけだが、それぞれの作品も2009年から2019年という時間を付帯していて、その場で紡ぐ「時間」と背後にある「時間」の両義性を孕んでその「時間」は進行してゆくという仕掛けになっている。その孕む「時間」の意味を知っているのは作者である我々だけとはいえ、そこに僕はある種の領域の果ての片鱗を感じて(信じて)その発表を客席で作曲者として感じ、見、そして聴いた。
今作品は情報科学芸術大学院大学、イアマス・タイムベースド・メディア・プロジェクトの一環で試演は一度2019年7月28日に行われている。
日々《変容の対象》8月[2009-2018]
“hibi”《an object of metamorphose》AUG 2009-2018
作曲:福島 諭+濱地 潤一(変容の対象)
映像:前田 真二郎(日々”hibi”AUG)
ピアノ:山内 敦子
サクソフォン:木村 佳
映像送出:森田 理紗子
システム:津曲 洸太
アドバイザー:三輪 眞弘
企画:IAMAS タイムベースドメディア・プロジェクト
この機会を経て、名古屋で初演を行った。
日々《変容の対象》8月[2009-2019]
“hibi”《an object of metamorphose》AUG 2009-2019
クレジット:
作曲:福島 諭+濱地 潤一(変容の対象)
映像:前田 真二郎(日々”hibi”AUG)
ピアノ:山内 敦子
サクソフォン:木村 佳
映像送出:森田 理紗子
システム:津曲 洸太
アドバイザー:三輪 眞弘
企画:IAMAS タイムベースドメディア・プロジェクト
『日々”hibi” AUG』は2008年からシリーズで制作されてい、毎年8月決められた規則に沿って撮影されている。以前から前田さんとは「日々」と《変容の対象》で何かできそうだと話していた。
具体的には変容が2009年から始まっている為2009年から2019年までの8月のそれぞれの11作品を初演では演奏した。年という単位では11年分の8月の時間がそこに在って映像はよりそれを具体的に表出しているのはそのメディアの優位性でもあり、音楽はある種そこに付帯する時間を表出することは難しいから、そこで見る、聴く、聴衆は映像によってその時間の持つ何かを感覚として触れることになる。11年分の8月という期間の時間。積み合わさった時間。それぞれの時間。表出される「今」という時間の背後にレイアーされている時間。
今作の特筆すべき点で言えば、前述にもある前田さん発案の映像送出を変容の対象の譜面から「読み取る」あるいは「呼び出す」方法を採用したことで、これらの行為は演奏家の行為であり、それを可能にするのは楽譜を「読める」者でなければならない。
映像が音楽に干渉せず、完全に独立して走るこの種の作品はいくらでもあるし、構造的にもそれは自然であるのかもしれない。今作品を今作品たらしめているのは、演奏家の特権である楽譜を「読む」という行為から映像送出が為される、、、そのシステムこそ、であり、ステージ上に存在する人間はその譜面というメディアによってのみ存在する。映像を「演奏」し、楽器とアンサンブルさせる。
それぞれの作品の個別の「時間」の重層の内包とその特殊な演奏形態からなる構造がステージ上に展開される様子を見るのは刺激的だった。2020年起こったことで最も素晴らしい出来事だった。
**
もう一つ。我々の《変容の対象》も2020年で12年の歳月を経て、作品も12X12の144作品のマトリクス(1月から12月の縦の12組曲、年度違いの同月の横の12作品)が組みあがったことが挙げられる。この12年の間に幾度かの年度別の変容の対象の初演も迎えることができたことも特筆に値する。
ピアニストの石井朋子さん、品田真彦さん、若杉百合恵さん、山内敦子さん、クラリネット奏者の広瀬寿美さん、サクソフォン奏者の五十嵐文さん、木村 佳さん、映像送出の森田 理紗子さんに謝辞を。
総括文に移ろう。
1月 執拗なロングトーンの組成。フラジオの多用。サックスに関して言えばひどく負荷のかかる演奏を強いる。この時の自身の着想がそれらを明確に意識していたであろうことは譜面を見れば一目瞭然のことのようにあって、それが全体をある強度を保ち続けた緊張のヴェールに包んでいるようにも思える。中盤の僕のシンプルな組織と福島さんの成す複雑な組織のアンサンブルの組み合わせに一つの着目点を見出す。「意識を持った複雑」さ、、、というような旋律の攻防(と敢えて言う)に一つの我々の標榜の姿、を一瞬垣間見る。変容の対象という作品の12年目の第1作品として何かを示唆している瞬間がそこに「記された」という意味でふさわしい作品になった。虚飾も装飾もなく僕はそう思う。
2月 あっという間に過ぎていってしまう時間。あるいは思考の流れ、映像。そういったものを含むものが音楽には在る。それは予め「音楽」というものに備わったものなのかもしれない。時に音楽は映像的であり、何か、、、を聴くものに訴えかけてくる。
サックスの演奏は循環呼吸を指示している、、、と、ここで書く手が止まる。
それは何処か在るべき場所。あるいは在るかもしれない場所。を、提示しているようにも思える。それが「この」時間の中に在るような、この音で編まれた時間は何かを内包している。
3月 ある不均衡さ。全体を覆うその不均衡さ、不安定さ。時間は進んで行くが、安定はどこにもないかのように映る。音の行方はそれぞれどこかのポイントに向けられて、、、は、いる。相互に干渉するアンサンブルの磁場はどこかその中心軸を探っているようで「それ」を掴むことをしない。あるいは拒むようにまるで仕組まれているようにも見える。かと言って、その不均衡な時間ははっきりと存在してい、常に停滞するような様相を示して進んでいる。斯様に「重い」時間を感覚的に捉えることが我々の日常に存するかと想像してはみても、在るようで無い、また無いようで在る。、、、もしかしたらこういった時間を感じさせるのは音楽というものだけが可能にするものなのかもしれない、、、とふと思ったりもする。確証は無いけれど。
4月 言語化することを拒む。囚われる時間。否応なく流れる。トポス。といったような言葉が頭の中に浮かぶけれど、その時書いた着想を思い出すことはできなかった。ある種の反射的な着想から組織を書き始め、始まったらその動線をなぞるように書く。そのまま時間を構築する。創造する。組み上げる。といったような言葉遊びも可能だけれど、そのような言語化をして書いているというわけではないのははっきりしていて、常に変容の当該作品のことは頭にあって生活している、、、と、いうことが当たり前の日常で、その日福島さんから送られてきた譜面を前に何かが僕の頭の中に小さな点のような「提示」が刻まれそれからそれを顕微鏡のようなもので拡大してゆく、、、ような。そうして書き始めたらその組織が「自らものを言う」ごとくある分岐点をおぼろげに浮かびあがらせ、数種類の行き先、あるいは一本の道を指し示す。その集積、、、書いていてこの月の作品だけのことではなく、12年変わらずこういったことをやってきたのだな、、、と。
5月 この作品もうまく言葉にできない。4月の作品は「聴く」より他無いような様相を持っていた。それとはまた違う。5月は動機の着想ははっきりと覚えているけれど、その後の展開の継ぎ目は一瞬迷いを示している。そこにははっきりと意識の分断があって、また再度着想を「書きながら」認識する作業を経て、書かれている。随分忙しく視点と意識が変化して書かれているけれど、ある種の文脈を掴むことはこの12年で互いに培われてきたのだろう組織にも見える。
6月 ある種の「強度」を持った組織が続く。その強度はサクソフォンという楽器の持つ一面を映している様にも思うし、僕が若い頃から標榜していたその楽器の個性の発露の延長線上に居る、、、様な気もする。言ってしまえばこの作品の様に、僕が実際サックスを吹くという行為と直接連動している様な、そんな作品も1年のうちに1曲、ないし2曲はある様な気がする。別の言い方をすればその他の作品は、僕が実際にサックスを吹くということとは直接的に連動しない作品として書かれている。福島さんの動機を受けて、おそらく最初は手探りで書き始めている。音形がアルトサックスの僕が囚われている音形の亜種であることから、僕の頭の中には実際に楽器を吹くイメージで着想していることは明らかだ。それはこの曲の最後までそうであるように今楽譜を確認して想像する。福島さんの書く組織と僕の書く組織が鬩ぎ合う結節点がダイレクトに表出されてそれがエンジンになって進む。分類すれば実際行われるインプロビゼーションに近い作品と言える。
7月 動機は僕から。動機の決定に目新しさは感じられないし、6月の感じを引きずっている様な箇所もある。この、あっという間に終わってしまう、、、というものにある種の「惹かれ」を感じるけれどおそらく、動機の時点でこの流れは決まっていた様にも思う。遡って見るに、、、ということだけれど、書いている最中は今の様な印象など微塵も無く書いている。おそらく僕は顕微鏡でその細部を見る、、、といった様なそういう書き方を選びがちで、その細部に「永遠」を宿す、あるいは「見る」といった様なロマンチシズムを僕はこの歳になっても完全に捨て去ることはできないのだろう。
8月 冒頭から8分音符と休符からなる無機的とも言える組織が続くが、このような組織の雛形は数年前の大垣ビエンナーレでの前田真二郎監督の映像作品「天皇考」のライヴ上映のために書いた作品に在る。こう言った組織をソプラノサックスで実際に演奏し、その音響体験をフィードバックしながらそれを引用するような状態で書いているはずだ。そもそも福島さんの動機にそう言ったアプローチが可能な領域を見つけたからそれが可能なわけだけれど、中盤の展開まではその着想が強く作用し意識されたことが楽譜を見てもわかる。中盤の「歌」の断片を想わせる組織に移行したのはその時(日)の自身の反応である可能性が高い(変容は書く日が違えば、おそらく違ったものになる、、、のは福島さんとも常々話していることだ)が、うまく機能しているように今は思う。後半にはまた導入の様式に戻るがそれも中盤に起こった磁場を思想的に回収している。印象に残った。
9月 この月ははっきりと目的があって、僕と福島さんの共同作品(サックスとコンピュータのための室内楽シリーズという作品群がある)の「respice finem」のサクソフォンの組織の組成の方法を楽譜に留めておくというものだった。変容と我々の別の文脈の作品の相互補完を仕掛けるという概念でもあり、また変容上で起こることにも興味があった。「respice finem」は組織の組成の方法が可変である作品で、スコアには10種余りの音列が提示されてい、言語スコアとともに奏者が読み取り循環呼吸奏法で演奏する作品である。だから当月の変容の組織はそれらの音列を使い組織されていて、また、実際に僕自身が数回の発表で演奏した組織に準じて書かれている。音列がそれぞれどんな組織を生むか、またそれら音列と音列の連結(循環呼吸奏法で演奏されるということはすべての組織が連結されなければならない)がどうやって為されるかこのスコアを見ればわかるようになっている。途中まで福島さんにはこのことをあえて言わずに作曲を続けてきて、月の終わりぐらいだろうか、直接話す機会が偶然あってそのことを話した記憶がある。こういうことは極めて稀であり、書いている途中に当月の作品について互いに話すことはほぼないから変容でも異例の月であったのは確かだけれど、変容の対象の一作品になっているのは変容の持つシステムの強さを表白しているようでもありその証左でもあるのだろう。記憶に残る作品になったし、またある時にはこのスコアが重要な役目を果たすことになればと思う。
10月 福島さんの動機から僕の採用した組織の在りようは、それが着想された時の記憶が奇妙にはっきりと記憶されていて、これしかない、、、という感触と共にあったことを思い出す。僕の組織の導入の音形は最後まで全体の組織の背後にあって、それがこの作品を書き進めるというエンジンになっている。全体の印象はだから「記憶」というイデアを想起させるようなものになっているような気がして、ある種の音楽の持ち得べき姿の一面を映し出しているのかもしれない。詩が持っている「永遠」という概念と同じく、音楽にも「永遠」や過去の映像、心理を映す鏡、思い出、といった心象を刺激しそれが洪水のようにフィードバックを起こす、、、というような体験を誘発する側面があるけれど、そのような気配を感じなくもないような、そんな作品ではないだろうか、、、気になる作品になった。
11月 この作品の最も興味深い小節は最後の9小節目であり、動機がこうあるべきだった、、、というような感慨を抱く。無論、最初の動機の提示があり、そこから始まった動線に沿って互いに編んでいったものだけれど、9小節目になって漸く理想の音形の姿が立ち現れた、、、というような感想が何故か自身の内に想起された。それだけ最後の小節が鮮やかに浮かび上がって見える。
12月 なんとも不思議な感覚を伴って時間が進んでいくが、福島さんからの動機の返答からどう言ったわけか、どう書いたのかほとんど記憶にない。変容ではよくあることだけれどわずかな歪みを伴って小節を跨ぎ進行してゆく意識は遡って楽譜の組織を見れば確認できるけれど、当時持っていた焦点を思い出すことができない。とは言っても複雑に入り組んだ意識の応酬はそこにあって、その反射(楽譜にその痕跡は克明に記されている)は変容そのものであるし、どこからか導かれたであろう(それはほとんど自身の意思の他の領域に存するものだ)組織の変遷をただ見れば良いという気にもなってくる。12年目の最後の月ということで何か特別な感慨、あるいは意識がなかったかといえば嘘になるけれど、それは書き始める前に起こることでしかなく、書き始めるとそう言ったことに干渉されることはなかった。当然のことでそこに譜面に定着された音群があり、その音によってのみ導かれる。普段変容に対峙している時間は変わりなく過ぎていった。福島さんの内部にある「響」は僕の内部にはないものだ。その「響」はこの12年変わりなくそこにあって僕はそれに対峙してきた。そしてその「響」は特別なものをそこに内在しているように思う。近年は組織の密度が増す方向に向かっている。それは意識的にそうしているようなことをいつかの折、話していたように記憶している。僕の方は変容の当初から組織の組成の密度が過剰に向くような傾向があって、そこをコントロールすることを考えるポイントも数年の中であるにはあったが早くにその制御の思考は奥に置いてしまった。ある種の作曲様式を形成するものが個人個人にあって、その発露を司るものは様々な要素によって成り立っている。それは蓄積された総体から枝付けされ反射を伴ってそこに表出される。変容は言うまでもなくその反射が肝でもあり、一月という時間は長いようで短い。福島さんの「響」もその短い時間の制約下でそうやって表出され、瞬時に譜面に定着されたものということが言える。12年はそれらの連続体と言えるわけで、それらは僕の内部にも影響を与えている。と同時に、違う意識が同時に走っている楽譜の「存在」を意識しないわけにはいかない。12月の楽譜を見てそんなようなことを考えてもいた。
第1稿2021年7月24日
第2項2021年9月2日
濱地潤一
《変容の対象》2020年総括文
2020年12月29日17時01分、2020年の12曲目を濱地さんと共に書き終えた。これで、2009年から開始された《変容の対象》は12年分の楽曲が揃ったことになる。いつ頃だったかは定かではないが、2人の共通認識として《変容の対象》は12年をひとつの区切りとしようということになっていた。1年12ヶ月の組曲が12年分存在すれば12(月)×12(年)の行列として、概念上では正方形の形に各曲を配置できることになる。このアイディア自体は映像作家・前田真二郎さんの作品『hibi』のアイディアとの関連で何処かで共有したものだったのかもしれない。実際に濱地さん、前田さんと私とでどこかで会話したような気もするが、あるいは『hibi』の設計プランにいつの間にか影響されてしまったのだろうか。いずれにしても、2人の12年間のやり取りが144曲の楽曲として置き換わり、大きな組曲群として完成したということになるのだろう。長い道のりかと思われた12年という歳月が、案外あっけなく過ぎ去ったようにも感じられる。最後12月の楽曲が終曲した際のメールのやり取りでは、濱地さんから「12年間お疲れ様でした。」という一言が添えられていた。少なからず胸が熱くなったのは忘れない。でも、これはなんの心の動きだったのだろう。2020年以降のCOVID-19の世界的な感染拡大の中にある今、和歌山と新潟に住む2人がわざわざ再会して祝杯を挙げるほどの状況にもなく、静かな日常の時間は今も淡々と流れている。
もともと《変容の対象》は、濱地さんと私が2008年頃に出会い、サクソフォンの演奏とコンピュータのリアルタイム・サンプリングを援用したライブ・エレクトロニクスの自由な即興演奏を何度か経験する中から、その演奏時間内で行われている思考のやり取りを別の方法で扱い記述することを目的に考案された試みである。原点である同じ空間・実時間を共有しながら行う即興体験では、それが事前の約束事が無い自由な即興であるが故に、その時々の音楽のあり様を良く聴き、相手の意志を読み、自らの姿勢を決定していくような判断が強く要求される。そしてその互いの判断が干渉/作用していくことで、結果的にはあらかじめ予想し得なかった景色まで導かれるというような事が起こり得るのであった。時間にすれば数分間の出来事であるとしても、そこで交わされる思考の密度は決して少ないものではない。たとえそのような高い密度は望めないとしても、やり取りの期間を一ヶ月に拡張し、作曲規則を整えることで、類似する思考のやり取りを丁寧に扱うことがこの《変容の対象》ではなかったかと今改めて感じている。その意味で、《変容の対象》は互いの人生と並走しながらも、もう一つ別の次元でいつも頭の片隅に存在する即興体験のようでもあった。この12年の間にも、社会的には大きな出来事、嘗て想像し得なかったほどの悲惨な出来事はいくつも起こった。そうした出来事に対して、私達の芸術はいつも無力であった。少なくとも《変容の対象》には対外的に何かを成すような力はほとんどない。あるとすれば、未来に対して演奏可能な楽譜を日々記していくことぐらいである。どんな世の中になろうと、濱地さんと私が一応互いに無事でさえあり、ネットワークが繋がる状態であれば《変容の対象》は続ける事ができる。ではなぜ、この現実の中において、この作曲行為は行われ続けなければいけなかったのだろうか。ここには現実に対して何かを表明する事を目指された楽曲は存在しない。もしもそうしようと思ったとしても、音楽の引力によって道筋はまた別の方向を向いていくものであったからだ。大袈裟に聞こえるかもしれないが、ここには人生とはまた別のもう一つの道筋、音楽の生命に関わる別の日常があった。現実があまりにも辛いというような場面においても、それに対して何かを成すという事では無く、少なくとも私には、その様な中で失われそうになる創意を維持するための体験を求めることがいつしか救いにもなっていたのかもしれない。そして、2020年以降のCOVID-19感染拡大の非常事態において、自らの発表の機会は一部の例外を除いて全て停止した。自らが人生において常に挑戦しようと考えてきた音楽の土台も失われたことになる。その中で《変容の対象》は影響も無く継続できたのは、もともと異なる空間、異なる時間を前提に構築された作曲行為であったためかもしれない。このような状況下において、《変容の対象》の音楽性に出会うことの意味は高まったとさえ感じられる。常に形を変えるその音楽は、濱地さん個人のものでも私個人の作曲作品にも見られないものが含まれる。未だ見ぬ音楽の美しさに触れたい。そうで無ければ、このような素朴なやり取りが長期に渡って続けられることは無かっただろう。
2021年からはどうするか、事前に濱地さんとは確認しつつこれまでの12年に対する新たな12年を刻むべく2021年1月から開始された。そして《変容の対象》は現在も続いている。2009年からの12年間を第一期《変容の対象》(phase1)とすれば、2021年からの第二期《変容の対象》には対称性を含ませるために各月の第一小節目を書く担当を入れ替えた。第一期の一番最初の小節は福島が担当したが、第二期は濱地潤一さんから開始されている。
1月:内省的。後半からバランスにやや乖離的なところが出るが大きな崩壊とはならず、それを別の地点に落ち着かせるだけの充分な長さも確保され丁寧に終結した印象。
2月:互いにリズミックなアプローチから開始される。ピアノは最初の動機の強度が次第に解けていくような形だが明確な着地点を見つけることなく不意に途切れるような形で終わる。サクソフォンの組織を聴くと以前濱地さんが循環呼吸で実際に吹かれていた音の組織の印象と極めて近いものを感じ当時の感触が蘇るような思いした。確かそのことは2月を書き終えた時にメールでお伝えしたように記憶している。もう長く濱地潤一さんの実際の演奏に触れていないとも気がつかされた。
3月:冒頭のうねるような濱地さんからの動機にどう対応しようかと迷った事は記憶している。ピアノも不安定に応答しているが明確にどこに向かうか分からないまま書き進め様々な地点を巡る。全体的にはピアノの低域も多めに使用され音域の広い重厚な印象は全体を通して感じられる。《変容の対象》12年間を通して3月は長めに展開されることが多かったが、それらの多くには明確な地点が定まらない迷いがみられ、2020年3月にもその迷いは感じられた。それがどういった要因から生じるものなのか、季節的なものなのか、考えさせられる。
4月:どっしりとしたピアノの動機に軽やかな旋律で濱地潤一さんが答えている。ピアノの高音で短音が鳴る瞬間からゆっくり目が覚めるように楽曲は展開している。伴奏的に始まったピアノのアプローチは徐々に和音を伴う旋律的な動きに変わり、一方のサクソフォンは背景に敷き詰められるタペストリーのように徐々に動きを制限していくように感じられる。もし実際の演奏が行われる事があれば、その辺りの互いの楽器のアプローチが徐々に入れ替わるような推移が感じられるものであって欲しい。
5月:濱地潤一さんからの単音/連打の動機から開始。第1小節目のピアノのアプローチを慎重に書いた記憶がある。中間部までの質感は音数はあれど動きは少なく静謐な一定の領域を保っていてる。中間に出るサクソフォンのロングトーンの後はその展開という印象だ。終盤まで徐々に変化の割合が増えて明快な音階の響きが見えた瞬間に消える。
6月:福島からの動機はややノスタルジックに響く部分が感じられる。濱地さんからの応答は必ずしもそれに添うものでもないが、大きく逸脱もしておらずその意味で両者の間合いはある一定間隔を保ちながら呼応している。終盤に向けて徐々にサクソフォンのリズミックなアプローチがピアノのリズムにも影響するように全体のテンションを徐々に上向きにさせている。その意味でしっかりとした両者の呼応は確立している。
7月:濱地さんからの動機で開始されているが、pianoも冒頭から対等のアプローチを行っている。シミュレーションでは50秒弱の長さとなっているが22小節目までやり取りは続いているから、思考の集積としては密度が高い。それでも冒頭から14小節目までは動機とそのバリエーションとして、ひと息で紡がれている感じがする。15小節目からのピアノのアプローチからは別のアイディアが生じるが、送られた日付が7月26日という下旬であることからも、結果的には終曲へ向けての準備として機能したようだ。丁寧に納まっている印象を持つ。
8月:福島からの動機。ややテンポは落とされたが先月のアプローチと似た音階的な、また音数の多いアプローチになっている。一方で濱地潤一さんからのアプローチは細切れた単音の提示が続く。ピアノとしては10小節目でひとつの節目を迎える。また15小節目後半から単音の連打が現れ始めて、次第に音数も減っていく。終始アプローチを大きく変えることがなかった濱地さんの単音の提示にピアノが次第に引き寄せられていくような、冒頭の印象からは考えられない静寂へ向かって行き終わる。
9月:濱地潤一さんからの動機から。ひと月前のアプローチから一転して、サクソフォンの高速なパッセージが続く。ピアノは応答のアプローチについてかなり時間がかかったように記憶している。日付を調べれば受け取って5日後ほどで返答はしているものの、当所ピアノのアプローチの方向性が見えないと感じその期間を長く感じたということかもしれない。結局、長い音価の和音の推移で答えるようにしている。やり取りの序盤で、濱地さんのアプローチには背後に何かのシステムが働いているように感じていた。実際、その予想はあっていたのだけれど実際に確認したのは曲が終曲した後である。それもあって、中盤頃からはほとんどピアノの響きから紡がれていく響きの推移に任せている。
サクソフォンに使用される音の変化には最低限の配慮はしたが、あまり意識しすぎてはいない。サクソフォンのアプローチの切り替わるタイミングはピアノの打鍵のタイミングと合わさる部分が多いから、その辺りの配慮は濱地さんのほうにあったのだろうと思う。
結局、ここで濱地さんが使用した音列とその配置方法は、濱地さん作曲《respite finem》の組織体系と関わっているものとなっている。この作品のライブ・エレクトロニクス部分の処理構造は福島の判断に一任されているが、いずれ近い未来に決定稿を作らなければいけない作品のひとつである。その意味で、この9月のサクソフォンパートは、《respite finem》演奏資料としても活用できるものとなるだろう。
10月:福島の動機から。実はこの動機を書くか書かないかの段階で、濱地潤一さん側のほうでの辛い出来事を知ることになる。そのようなタイミングで《変容の対象》のやり取りを行うかどうかという迷いが無かったかと言えば嘘になるが、結果的にはやり取りは続いた。10月4日に第1動機を濱地さんへ送り、約3日後に帰って来た返答はやはり強い印象が残っている。2小節目は4分の2小節でこれまでのやり取りからすればかなり音価の少ない返答といえる。実際、タイで繋がれ四分音符分伸ばされた音のみであるので、ここで新たな楽想の提示はされなかったことになる。
中盤から後半にかけて楽曲は徐々に静かな熱を帯びてくるようでもあるが、抑制の範囲内にある。一見して気がつきにくいが、サクソフォンには7小節目と11小節目に同じ音型が書かれている。こうした反復は《変容の対象》ではあまり多くの例はない。私個人としては過去に何度か試みた事もあるが、書き直しのできない《変容の対象》の作曲システム上あらかじめ全体を捉える事が難しく、上手く機能しないと感じている。ただ、この10月のサクソフォンの動機の反復は印象がそれぞれ全く異なっていて、音楽的に自然な形で忍ばされた貴重なピースのような印象がある。
この曲に関しては、ピアノは常に抑制しつつ澄んだ響きで演奏されるべきだと感じている。
11月:濱地潤一さんからの動機。スラップタンギングと旋律的なアプローチが混在するもの。1小節の持つ拍数も28拍と長めになっている。対するピアノの応答はあまり気の利いたアプローチには聞こえない。積み上げる音は多くともあまり機能しておらず、色彩に欠ける。9小節目からの崩れ落ちていくようなピアノのアプローチには急にやや紫がかった色彩がみなぎるが、音楽的には一種の覚醒の状態をもたらす急激な展開にも思える。
12月:福島の動機から。1小節目の和音はピアノに触れながら響きを確認した。濱地潤一さんからの返答のアプローチを待ってその後の展開は決定されていったが、1小節目の濱地潤一さんからの返答には特にmellowな印象を受けたのを覚えている。12年の最後の曲になることはお互い少しは話してはいたが、必要以上に意識することはなかった。
冒頭の動機の印象から全く身動きが取れなくなる月もあるものの、この12月に関してはそのような事はなく、自由に展開した。お互いに聴きあって道筋を決定している印象もあるからその意味では《変容の対象》らしい即興となったのではないだろうか。終止に向かう感じ、どことなく雲に紛れるように消えていくこの感じは144曲目の終わりとしては適切なものかどうかは分からない。ただ、この曲が生まれて、終わるというその佇まいは肩肘を張らない有り様があり、無理な展開は避けて音楽の有り様に身を任せるような自然な姿が感じられる。
日常に比べれば音楽は遥かに抽象度の高い記号の集まりによって成り立っている。音楽そのものに形はないが、結果的には一種の造形物としてさえ認識され得る不思議な芸術の領域だと思う。実時間上で表現されるべき音楽の形は、あらかじめ楽譜によってその姿を留めておくこともできる。また、音楽に接して、その印象から自らの心の中にその音楽がどのように変化し、どの様な色彩を留めていたかを記憶する事もできる。当然、楽譜があらかじめ留めておける領域には限界もあるし、記憶がいつも正確だとは限らない。演奏においては奏者の解釈や身体の状態が極めて繊細に作用する。だから、音楽はいつもその有り様を変える。そして何より、音楽はいつもこの実時間の流れの中でのみ姿を現すものなのだ。
自由な即興が、実時間の中で極めて高い意識の集中により生み出されていくものだとして、それが毎回ベストの結果に繋がるとは限らない。(特に私にとっては、)いつも自分の身体はエラーを引き起こすからである。ミスと思える1音がその後の音楽のあり方に決定的に影響してしまうのはとても残念なことである。これをもっとじっくりと一手一手丁寧に進めるやり方として《変容の対象》は考案されたが、これが単なる即興時間の延長にならなかったのは幸いだった。一ヶ月内での思考の変化が、五線譜に圧縮されて留まっていくような様子や、1曲の中に2者の意志が互いに干渉し、拮抗したり寄り添ったりする様子がここには写しとられているからだ。作曲規則の(2)にある交換形式の作曲法は、常に相手からの提示に対して自らのアプローチを決定していく姿勢が求められ、作曲行為の本質的な原動力となっていた。そして、相手に渡した楽譜を後から編集する事はできない、とした(4)の規則は、即興の一回性のあり方を模しているものであったが、これによって、音楽を生み出す各瞬間を人生の日常と接触させながら歩んでくることができた。その意味で、《変容の対象》の各曲は音楽的に決定的な完璧さを求められて作られた楽曲などでは無い。人生がそれぞれの人にとって1つの長く切実な即興体験であるのと似て、日常の中で行われた2名の作曲者による思考のやり取りを音楽的な抽象度に高めてそのまま写し取ったものである。それがどのようなものだったかは、この12年間の楽曲の全てに留まっている。過去を顧みることはできても修正することはできない。完璧な音楽では無いかもしれないが、それらを改めて見直すときに決して悪い気持ちにはならない。そう思える理由のひとつは、私にとってもう一人の作曲者である濱地潤一さんがこの《変容の対象》の作曲において、常に音楽芸術への最善を尽くしてくれたからだ。
2021年1月7日 ~ 中断
3月18日再開 ~ 中断
6月3日再開 ~ 中断
9月2日再開 ~
2021年9月4日
福島諭