+ 《変容の対象》2015年版
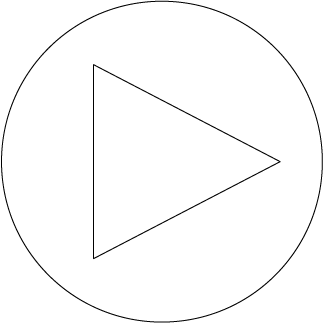 00:00 [00:00]
00:00 [00:00]
作曲: 福島諭 + 濱地潤一
《変容の対象》2015年版総括文
2015年は動きのある年だった。思い返せば良いことも悪いことも、そして今後どうなるのかよく分からないことも含めて様々な事柄が飛び交っていたような感覚を持つ。ただ、個人的にはその都度やるべき事に集中もできたから失敗も含め心静かに日々を送っていたようにも思う。環境的な意味で大きな変化は3月に引っ越しをして、自分が大学まで暮らした場所、そしてリフォームこそしたが育った家に戻ることになったことだ。そのときの感覚は実に不思議なものだった。自分の遠い記憶が刺激される景色がそこかしこにあり、またそれらは全体的に少し尺度が小さくなって見えたり、或いはそこにあったはずのものがなくなっていたりと、少しの混乱も覚える。時が流れたということも実感した。
個人の作曲としては、五管の木管アンサンブルとコンピュータのための《春、十五葉》、そして混声4部の合唱曲《Eupatorium fortunei》の2曲を作曲し演奏の機会に恵まれた。
きっかけは第18回文化庁メディア芸術祭における受賞(《 patrinia yellow 》for Clarinet and Computerでの優秀賞)だろう。現代音楽においてある意味伝統的な作曲スタイルの作曲作品が、メディア芸術と呼ばれる比較的新しい視点で見直されたということでもあり、その意味でも貴重な機会だったと考えている。とにかく、受賞をきっかけに普段目にしない人たちに届ける機会が幾分増したというのは事実だし、ある種の責任を頂けた年であったとも思う。
そんな中での《変容の対象》の作曲はかなりの割合で感覚的な作曲を行っている。これは個人作品の作曲において音や数の関係性に頭を割いていた反動とも思える。《春、十五葉》に関しては作曲を開始した2月頃から9月に行った再演が終わるまでずっと考え続けていたような印象もあるから、《変容の対象》ではあえてそのようなアプローチは避けたという事かもしれない。《変容の対象》の1月 2月あたりは、意識的に音のリズミックな連打を取り入れるようにして書いた記憶はある。しかし、その他は各月で解説として書ける事は例年よりは少ない。なぜそう書いたかについて明確な理由がないからだ。感覚的に書くということには、制約無く音楽的表現の幅を広げる姿勢で書くということも意味するが、ピアノに関しては結果的に充分成功しているとは思えない。上半期に躍動的な表現は集まったものの、下半期では濱地潤一さんとのやり取りそのものも少なくなっている。これは、パソコン環境の変化も関係しているかもしれない。2015年はメインとなるラップトップを新しいものに移行した。それに伴って前のパソコンで使えていた楽譜作成ソフトが新しい環境では使えず、ソフトの移行も進まなかった。結局その問題は2016年2月現在でも続いている。濱地さんと私のほうで使えるソフトを共通にする必要もあり、問題が幾分入り組んでしまったのだ。ともかく、長い電車の移動時間を使って書いていた作曲リズムが崩れてうまく立て直せないまま2015年は終わったとも言えよう。
1月[the direction of a magnetic field]
冒頭文は福島諭による。特に深く考えず冒頭文は決めていたと思う。磁場と音楽的な引力についての意識を取り入れてみたかったということだったかもしれない。1月15日に第1小節目をスタートさせている。実際は濱地潤一さんからの返答をうけて、あまり冒頭文を意識せず音楽は進行した。その意味でピアノの組織も深くは考えず、何か即興的に音楽的な進行に任せたと思う。唯一そうすることが冒頭文との整合性を保つことでもあると感じていた。
2月[music of anonymity]
冒頭文は濱地潤一さんから、「匿名性の音楽」の意。2月12日頃に受け取る。
今年の組曲の中で一番長い曲になった。終わり方の長い休符が印象的だが、終わり方については自分自身は落としどころをなかなか見つけられなかったと記憶している。中盤までのピアノとサクソフォンのアプローチが通常あまり見られない独特の親和性を保っていたためでもあるかもしれない。このような状態になると意識的に終わらせようと思わない限りなかなか終止へ向かわない。
3月[labial mist]
冒頭文は福島諭による。これも至極感覚的な冒頭文と言える。この時期の湿った気候からの印象を冒頭文へ投げかけた気もするが、一般的に新潟の3月は霧がかっているだろうか?特に何か特別な経験をした覚えはない。
ピアノは前打音を多用した表現を使用している。6小節目からの低音の連打は楽曲の印象を変えている。全体を通してそれらが安定したフォルムに収まっている印象がある。決して明るくはない響きのトーンに冒頭文との整合性はやや見て取れる。
個人的な事で書けばこの時期は引っ越しと作曲家桑原ゆうさんのピアノ曲の多重録音のお手伝いなどを行っていた時期でもあった。
4月[extrema]
冒頭文は濱地潤一さんによる。「極値」。
この時期に5月に新潟で発表予定だった《春、十五葉》のための打ち合わせを濱地潤一さんとSkypeを行っている。作曲時期からして早い段階とは言えないから、気持ちは《春、十五葉》初演に向けて不安も多かったと思う。しかし、《変容の対象》での内容はそのあたりの心象を表しているとは思えない。《変容の対象》はそういった意味で現実の心象とは関係の無い、もう一つの現実として存在している領域でもあるように感じられる。
5月[fifteen leaves]
冒頭文は福島諭による。冒頭文は5月に新潟で初演された《春、15葉》(spring, fifteen leaves)というコンピュータと五管の木管アンサンブルのための曲から引用でもある。アルト・サクソフォンのesのロングトーン、特に循環呼吸によって実現される音は《春、15葉》内で試みられた、そして実際に濱地潤一さんによって実現された領域でもあったが、この月の《変容の対象》でも印象的に使われている。ピアノの組織は《春、15葉》内で使用された音列処理のリストから使用されているのである程度統制された響きの連続がある。
サクソフォンのロングトーンと超高速の音の組織(いずれも循環呼吸の中で実現される)の対比も印象的かつ効果的に機能しているの感じる。実際の演奏でも聴くことができたら、、と思わずにはいられない。
6月[iron nails run in]
冒頭文は濱地潤一さんによる。メールで「鉄の釘が打ち込まれたる者」と意味も書かれていた。6月13日に受け取っている。
濱地さんからの第一小節目にどう答えるか最初は難しいと感じたが、思ったよりも早く書けたように記憶している。そのピアノの組織の様子に結局縛られている。その後大きく変化することは叶わなかったが、冒頭文からの整合性を考えても問題の無い範囲で楽曲は続いていった。後半の濱地潤一さんのロングトーンがここでも印象的に扱われている。ピアノは終始一定の重さを持った要素を展開させている。終止の印象は他には観られない領域も少し感じられる。
7月[1 4 3(1)]
冒頭文は福島諭による。1小節目を7月17日に送っているからあまり時間の無い中でやり取りは続けられた。冒頭文は機能和声におけるI度からIV度への進行、そしてIII度へ移ったときにこれを再びI度として読み直すという事だ。和音の変更はLisp言語で簡単なプログラムを組んで明確にして行っている。
やがて、決められた和音からどの音を選択するかは小節の上部にメモとして記載するようになった(pianoパートのみ)。濱地潤一さんにはこれらのことは事前にお伝えせずに作曲を進めていった。また、pianoパートの6小節目のDの音から和音進行を変更している。
以下、Lisp言語でのプログラムを記しておく。
*進行は主音を0として半音階で数え、I-IV-IIIを考える。:0 - 5 - 4
variable cell1 = {0 5 4}( < 進行についてのリスト)
variable chord1 = {0 4 7 10}( < I に対する和音構成のためのリスト)
variable chord2 = {0 4 8}( < IV に対する和音構成のためのリスト)
variable cell2 = {0 5 10} ( < 6小節目から変更した新たな進行についてのリスト)
variable chord1-2 = {0 3 6 10}( < I に対する和音構成のためのリスト)
++(函数:”oct(num)” )
; think octave 0 to 11
function oct(num)
num % 12
end
++(函数:”newc_trans(lst, num, trans)” )
;lists + numbers + transpose
function newc_trans(lst, num, trans)
loop with newc = {}
for i from 0 to length(lst) - 1
set newc &= oct(nth(lst, i) + num) + trans
finally newc
end
end
+++(以下は計算を実行)
print( t ," = ", note(t) )
print( newc_trans(cell1, 0, 60) ," = ", note(newc_trans(cell1, 0, 60)) )
print( newc_trans(cell1, 0, 64) ," = ", note(newc_trans(cell1, 0, 64)) )
print( newc_trans(cell1, 0, 68) ," = ", note(newc_trans(cell1, 0, 68)) )
{60 65 64} = {"c4" "f4" "e4"}
{64 69 68} = {"e4" "a4" "af4"}
{68 73 72} = {"af4" "df5" "c5"}
以上をベースラインとして繰り返し。
print( newc_trans(chord1, 0, 60) ," = ", note(newc_trans(chord1, 0, 60)) )
print( newc_trans(chord1, 0, 64) ," = ", note(newc_trans(chord1, 0, 64)) )
print( newc_trans(chord1, 0, 68) ," = ", note(newc_trans(chord1, 0, 68)) )
{60 64 67 70} = {"c4" "e4" "g4" "bf4"}
{64 68 71 74} = {"e4" "af4" "b4" "d5"}
{68 72 75 78} = {"af4" "c5" "ef5" "fs5"}
Iの和音に対しての上のコード。
print( newc_trans(chord2, 0, 65) ," = ", note(newc_trans(chord2, 0, 65)) )
print( newc_trans(chord2, 0, 69) ," = ", note(newc_trans(chord2, 0, 69)) )
print( newc_trans(chord2, 0, 73) ," = ", note(newc_trans(chord2, 0, 73)) )
{65 69 73} = {"f4" "a4" "df5"}
{69 73 77} = {"a4" "df5" "f5"}
{73 77 81} = {"df5" "f5" "a5"}
IVの和音に対応する響き。
print( newc_trans(chord1, 0, 64) ," = ", note(newc_trans(chord1, 0, 64)) )
print( newc_trans(chord1, 0, 68) ," = ", note(newc_trans(chord1, 0, 68)) )
print( newc_trans(chord1, 0, 72) ," = ", note(newc_trans(chord1, 0, 72)) )
{64 68 71 74} = {"e4" "af4" "b4" "d5"}
{68 72 75 78} = {"af4" "c5" "ef5" "fs5"}
{72 76 79 82} = {"c5" "e5" "g5" "bf5"}
IIIの和音に付加する響き、これはIのものと同じとする。
++(6小節目からの構成音について)
variable cell2 = {0 5 10}
音程差を上記に変更する。
6小節目のD音から開始。
print( newc_trans(cell2, 0, 62) ," = ", note(newc_trans(cell2, 0, 62)) )
print( newc_trans(cell2, 0, 60) ," = ", note(newc_trans(cell2, 0, 60)) )
print( newc_trans(cell2, 0, 70) ," = ", note(newc_trans(cell2, 0, 70)) )
print( newc_trans(cell2, 0, 68) ," = ", note(newc_trans(cell2, 0, 68)) )
print( newc_trans(cell2, 0, 66) ," = ", note(newc_trans(cell2, 0, 66)) )
print( newc_trans(cell2, 0, 64) ," = ", note(newc_trans(cell2, 0, 64)) )
{62 67 72} = {"d4" "g4" "c5"}
{60 65 70} = {"c4" "f4" "bf4"}
{70 75 80} = {"bf4" "ef5" "af5"}
{68 73 78} = {"af4" "df5" "fs5"}
{66 71 76} = {"fs4" "b4" "e5"}
{64 69 74} = {"e4" "a4" "d5"}
以上ベースラインに繰り返し。
print( newc_trans(chord1-2, 0, 62) ," = ", note(newc_trans(chord1-2, 0, 62)) )
print( newc_trans(chord1-2, 0, 60) ," = ", note(newc_trans(chord1-2, 0, 60)) )
print( newc_trans(chord1-2, 0, 70) ," = ", note(newc_trans(chord1-2, 0, 70)) )
print( newc_trans(chord1-2, 0, 68) ," = ", note(newc_trans(chord1-2, 0, 68)) )
print( newc_trans(chord1-2, 0, 66) ," = ", note(newc_trans(chord1-2, 0, 66)) )
print( newc_trans(chord1-2, 0, 64) ," = ", note(newc_trans(chord1-2, 0, 64)) )
{62 65 68 72} = {"d4" "f4" "af4" "c5"}
{60 63 66 70} = {"c4" "ef4" "fs4" "bf4"}
{70 73 76 80} = {"bf4" "df5" "e5" "af5"}
{68 71 74 78} = {"af4" "b4" "d5" "fs5"}
{66 69 72 76} = {"fs4" "a4" "c5" "e5"}
{64 67 70 74} = {"e4" "g4" "bf4" "d5"}
Iの和音に対しての上のコード。
print( newc_trans(chord2, 0, 67) ," = ", note(newc_trans(chord2, 0, 67)) )
print( newc_trans(chord2, 0, 65) ," = ", note(newc_trans(chord2, 0, 65)) )
print( newc_trans(chord2, 0, 75) ," = ", note(newc_trans(chord2, 0, 75)) )
print( newc_trans(chord2, 0, 73) ," = ", note(newc_trans(chord2, 0, 73)) )
print( newc_trans(chord2, 0, 71) ," = ", note(newc_trans(chord2, 0, 71)) )
print( newc_trans(chord2, 0, 69) ," = ", note(newc_trans(chord2, 0, 69)) )
{67 71 75} = {"g4" "b4" "ef5"}
{65 69 73} = {"f4" "a4" "df5"}
{75 79 83} = {"ef5" "g5" "b5"}
{73 77 81} = {"df5" "f5" "a5"}
{71 75 79} = {"b4" "ef5" "g5"}
{69 73 77} = {"a4" "df5" "f5"}
IVの和音に対応する響き。
8月[short attack, short duration]
冒頭文は濱地潤一さんによる。冒頭文自体が音楽的な表現と直接結びつくものでもあったので、意識してその制約の中に自らの態度も置いている。良い意味でこれまでの流れを断ち切るものになった。欲を言えばもう少しやり取りが続いても良かったと思うがそれは全体を聴き直しての事でもあるから、作曲時には判断しづらい領域でもある。
9月(冒頭文なし)
一つ前の月の冒頭文が楽曲と強い結びつきを持っていたので、この月は意識的に冒頭文を書かなかった。事前の自分の想定ではかなり自由に展開をつけることも可能だとも思ってもいた。ただ、結果的には小節単位で大きな変化を取り入れるようなアプローチにはならず、聴き返せば驚くほどどこへも向かっていない。一つの領域内で時間を費やしている。冒頭文を書かなかったことの私からの意図を事前に濱地さんへ伝えていたわけではないので、当然の結果でもあるがこれは逆説的にではあるが、いかに冒頭文が2人の意識の統制を行っているかも明確にしていると思う。
10月[blue]
冒頭文は濱地潤一さんによる。短い曲だがやり取りの頻度は10往復だから少なくはない。1曲のボリュームとしてはもう少し長くても良い気もしたが、それは今更変えようもない。fineを向かえた時点で濱地潤一さんからは「3、5、7度の♭を主題に組織しています。blueはだからblue noteのblueでもあるんです。」という内容が明かされた。この月のピアノの処理はただ単に濱地さんから提出された旋律をある範囲ですくい取って、縦に並べて和音にしたり、逆行させたりという簡単なやり方を採用している。響きの統一感で濱地さんは少し驚かれていたような発言もどこかでされていたと記憶しているが、こちらは濱地さんの旋律に対して新たな和音を付けようという意識は全く働いていなかったというのが本当のところだった。ただ送られてきた旋律の音をサンプリングして並べ替えを行うこと、それがこの月で自分に課した約束事だった。
11月[think melody]
冒頭文は福島諭による。メロディーについて考えたい、という気持ちがあったのであるが、結局ピアノ自体はあまりメロディアスには振る舞っているとは思えない。結局やったことと言えば、意識的に動機の反復を取り入れるようにしたことくらいであろうか。あとは、意識的に異なった動機を加えるようにもしている。何度か場面展開するのはそのためである。この月の変容を終えて結局自分はメロディーについて何も分かっていないのだという気持ちになったのを覚えている。また、終盤で13小節目の濱地潤一さんのアプローチが素晴らしいと感じ、メールにもそのように書きお伝えした。冒頭文との整合性はともかく、キュートな小品にはなったという認識はある。
12月[segment]
冒頭文は濱地潤一さんによる。分節で音楽が変化・展開していくような様相を想起しつつ作曲を進めた。しかし、ピアノに関していえばあまり大きな飛躍には繋がっていない。作曲当初は曲の内容と関係無く、この月に初演された合唱曲《Eupatorium fortunei》の話題から詩と音楽に関する意見交換が頻繁に行われていた。また、この月は濱地潤一さんが岐阜で前田真二郎さんの上映作品にライブで参加する機会もあった。そこで、濱地+福島作品などのCDRを詩人の松井茂さんへ濱地さんがお渡しし、松井茂さんから丁寧な感想を頂いたり、というやり取りがあり、朧気ながら詩について思索を巡らせた月ともなった。合唱曲の録音は濱地さんへ送りますといいながら、本番の録音が送られてくるまで待とう、などと思いながらいたら結局送れなかった。
《変容の対象》に関していえば、終盤で濱地さんから送られてくる旋律に終止感を何度も感じる、という経験をした。何となくそれで、私も終止に向かってしまったのだが、後で確認すると濱地さんにはその気はなかったようだ。完成した状態でいま聴きなおしてみても、強い終止感はそれほど感じられないから不思議である。これまでの《変容の対象》の12月の作品としては極めて短い作品となった。
2016/01/01~2016/2/24(第1稿)
2016/02/29(加筆・修正)
福島諭
《変容の対象》2015年版総括
1月(the direction of a magnetic field)
括弧内は譜面最初に記されている冒頭文で福島さんによる。この1月は新潟で《変容の対象》2013年度版抜粋の初演、さらに砂丘館での発表、日をおいて新潟県政記念館での演奏(2つは自身の演奏だ)などがあり、その期間がありながらこの作品のやりとりの密度は、、、と思わせられる。細部をどう書いたかは明瞭に回顧できない。切迫した時間があっただろうことはその日程だけ見てもあきらかで、おそらく自分の演奏に関する準備もあったから冒頭文の指し示すものを想定しながら反射的に書いているだろうことは想像に難くない。自分で書いていながら1年前のこのスコアをどう書いたのかさっぱり思い出せないのはこの1年間(2015年)の長さ、、、実際演奏の機会などそれぞれ今思い返しても記憶がどうも遠景のようにうつる、、、故なのか遠い記憶という感触しかなく、こうはっきりと音符として刻まれているものを見ても最早自分の手を遠く離れているものとしてそこに在り、ただそのスリリングな現象のみが妙に切迫して迫ってくる。18-19小節目の自分の組織などは自身の演奏の身体的反射を想定して書いているのではなく、頭にある着想を音符に変換する折に明確なものがあって書いてあるが、言語化できるかは別にして、そういう書式はその2小節だけではないし、実際音符が指し示すその着想を改めて探りたいぐらいの引力はあるけれど今はなかなか難しいようだ。ひとつ書き加えるなら、今月の作品は突出した組織間(ピアノとサクソフォン)の言ってみれば攻防が激しく展開されていてそれは福島さんと自分の思索の衝突がなにか結実したものを現しているように書かれていて、それは作品冒頭からfineに至るまで減速しない。自分にとって特別な作品となった。
2月(music of anonymity)
冒頭文は自身による。匿名の音楽とでも訳されようか。記憶されない音楽という意識もあった。全編を通して脈絡のない音の配置、装飾音が書かれていて、時に不意に強い調性の像が結ばれる。それがひとつの重要な要素としてあるのだけれど、自分がコントロールしてそうあるのではなく、福島さんの組織と合わさってそういう像が結ばれるのは変容の所以でもあるし、実際improvisationの演奏の場でも起こる現象のひとつでもある。けれどこれは音楽の、平均律の音楽のある種の特性でもある。作品の後半では分散和音的装飾音符を多用しているがそういう引力に引かれた結果で、流れという避け難い要素も機能しているのが見える。2月は福島さんの作曲作品《patrinia yellow》の文化庁メディア芸術祭優秀賞受賞の展示と演奏が東京であり、自分も《bundle impactor》の奏者として演奏し、東京新美術館の展示も見る事ができた。高橋悠、高橋香苗さんのスピーカーシステムが印象的に配置された良い展示だった。話は作品にもどるけれど、何か明確には形容し難いのだがこの月の作品も自分にとっては特別な何かを留めているように思う。匿名性というのは自分の羨望の対象のひとつでもあるけれど、実際は自分とは離れられない、、、というのも避け難い故のナラティブ性みたいなものもそこに含まれているようで、音楽をそこにどうにか近づけようとするコンセプト自体に意味を見いだしたかったのかもしれない。
3月(labial mist)
冒頭文は福島さんによる。9-12小節目の相互間の組織による干渉渦がスリリングだ。「スリリング」という形容は現代音楽なんかではほとんど意味を為さない。けれどそういう領域は音楽には確かに存在するし、意味を為さないといって机上で考えている範囲では反証は実は充分ではない。軽蔑すれど軽視できないというものだってあるにはあるものだ。実際ジャズ ではインタープレイがスリリングであるという形容は良く語られる語法であるし、しっくりもくる。何せ目の前でそれがimprovisedされているわけだ。それはスリルを感じる。一方こういった譜面での相互間の旋律は予め書かれてあり、定着された後の姿であるからスリリングかどうかは実は問題ではないのだが、あえてスリリングという要素が顕在化しているような譜面であることには間違いはないように思う。《変容の対象》のひとつの特性であるかもしれず、しかもそれは完全に作曲者のコントロール下にいない現象の顕在化の姿としてあり、そこが特筆すべきこの作品のある視点であることは疑いようがないことに於いて強く印象に残る作品になった。
4月(extrema)
冒頭文は自身による。改めて確認してみても冒頭文との親和性はあまりない。自分の動機からしてそうだ。作曲中、提示された、あるいは書いた実際の音に引っ張られて結局その概念を反映できずに終わる事はままある。何か起こるのを待つ、、、みたいな局面も変容ではあり、結局待ってはみたけれど終わってしまった。そういうところなのかもしれない。
5月(fifteen leaves)
冒頭文は福島さんによる。単音の循環呼吸の採用は福島さんの作品《春、十五葉》からの引用だ。(ラフォルジュルネ新潟2015が初演)つまり直接冒頭文を参照しているということになる。装飾音の挿入から暫くして高速のフレーズに移行するが、この部分は任意で倍音操作する指示を書いた。実際のフィンガリングで得られる(はずの)旋律が必ずしも出力されない。そこでは音符の表記のまま出力されても良いし、倍音操作によるものでも良いということだ。肝は単音のロングトーンの循環呼吸奏法であるのだが、信じられないぐらいタフな奏法(超絶と言って良い)だ。
循環呼吸、サーキューラブリージングという奏法について、この奏法を単に難度の高いひとつの奏法と認識するか、あるいは「概念」として例えば一例として「神の領域に触れるため」のものとして捉えるかでは自ずと意味性はちがってくる。管楽器を吹いていながら、まるで呼吸していないかのような「現象」を奏者は表出する。聴衆、あるいは第三者の意識、認識の及ばないところの領域ではそういう「概念」が機能して走っていたとしてもなんら不思議ではない。作曲ということはそういう領域を常に孕む。
6月(iron nails run in)
冒頭文は自身による。「鉄の釘が打ち込まれたる者」動機をもう少しいかせた書き方もできたはずだが、そうしなかったのは何故だろう。と今は思う。1小節目の動機を福島さんは5小節目、6小節目でslide-variationさせていて、次の動機に繋げる推進力を得ている。12小節目からの14小節目のような組織はソリッドで内省的な響きを持っている。fineに至る終止もその気配を置き去りにしているという意味に於いて魅力的な小品となっていると思う。
7月(1 4 3(1))
動機は福島さんによる。全体を通して福島さんの組織する和声的うつろいの隙間を埋めるように自分の組織が走っているけれど、度々見え隠れする言わば組織の常套句みたいな個所が気になるといえば気になる。しかしながらこういう分裂的な組織を延々、ある秩序、そう、認識不可能な秩序というような概念には感覚的ではあるがなにかしらロマンすら感じてしまうのも事実だ。実際こういった組織形成がそれをうまく体現できているとも思えないけれど、いつか書きたいとは思わせられた。作品は冒頭文が数列ということもあって自分はそれには干渉されずに相当感覚的に書いていた記憶がある。感覚は最も懐疑の対象となるものでもあるけれど、それを表出するレヴェルには自ずと階層があり、それを認識したうえで感覚というものを概念化する、しようとすることもある領域では可能であると少し考えてもいた。中盤のブレスの無い箇所は循環呼吸でしか再現不可能だが、切迫した時間形成に於いては必要だと思う。この月も印象に残る作品。
8月(short attack,short duration)
冒頭文は自身による。2つの指示を否応なく想定しなければならないもので、幅をもたせるような冒頭文ではないものをこの時書きたかった。実際こういう指示は譜面に対峙する思考の在りようをシンプルにしてくれたようにも思う。方向性は決まっていて、あとはそれぞれ対する局面において何を選択するかだけが問題となるような。ただ、その選択に関しては細部を追って行くような慎重さと注意深さがなくてはならない。音価、音高、どこにそれを配置するかなど、結構時間を要した小節もあったように記憶している。今確認してみて冒頭文がとても強く機能している作品であり、このソリッドな佇まいの楽曲は冒頭文が成功していることを示しているようで、可能性としてはもっと指示の言葉を増やすなどすることによって出来得る作曲もあるように思う。印象としては概念と音がぴったりとしている。実際の演奏で聴きたい。いつか。
9月(冒頭文は無し)
動機は福島さんによる。3小節目は書くのが難しかった。そのことだけ覚えている。念頭には淡々とほぼ同じ組織構造が続いてゆくということを決めていたように思う。自分の組織に限定して話せば、結局何も始まらず終わってしまったようなそんなfineをむかえた。この月は書くのがちょっと難しい。
10月(blue)
冒頭文は自身による。この月は音階とその3度、5度、7度の♭で組織を形成していった。blue noteの概念だけかりたもので、bluesとは何の関係もない。つまり記号としての処理でありそういう組織構造だというだけの意味でしかない。ある固定された概念の「読み違え」を意図的に起こすということだ。楽曲の表層的にそういった思考方式が反映されて聴こえるということはないけれど、重要なのは楽曲「そのものも」さることながら、その構造形成に到った思考の結節点のレイヤーだと言うことは自分の演奏する作品に低通する概念でもある。
11月(think melody)
冒頭文は福島さんによる。冒頭文の参照で考え込んで書いていたことを思い出す。メロディーということをどう考えるか、、、ということだったが、言葉のシンプルさとは裏腹に、ことはそう単純では無い。結局焦点を結べないまま5小節目では自分はひどい間違いを犯している。ああ書くべきではなかったと思う。多分思考停止に近い感じでただ書いてしまったように見える。その後はとって付けたような組織ばかりが目に付き、楽想に輪郭を持たない。ようやく13小節目に至って啓示を得たような気がしたが、期日は迫っていてそのままfineとなった。
12月(segment)
冒頭文は自身による。何と言うか、あっと言うまに終わってしまった感じ。割と自覚的に冒頭文と対峙した記憶があるけれど、楽想にうまく反映できているとは言い難い。この手の冒頭文のような思考法は毎年何か言葉を変えて仕掛けるけれど、ことごとく失敗(何が失敗なのかははっきりしないけれど)する。例えば当年の1月の作品の方がよっぽどsegmentalだ。
2016年1月2日から9日深夜にかけて記す。(第1稿)
2016年2月29日加筆。
濱地潤一